コラム
肺がんの余命は?ステージ別の生存率や原因・症状も解説

肺がんは、日本におけるがんの中でも死亡率が特に高い疾患の1つです。早期にはほとんど症状が現れないことも多く、気づいたときにはすでに進行しているケースも少なくありません。
そのため、「余命はどれくらいなのか」「ステージによって生存率はどう違うのか」といった情報を知っておくことは、治療の選択や心の準備をする上でも大切です。
この記事では、肺がんの主な原因や症状の特徴をはじめ、ステージ別の生存率や治療法についてわかりやすく解説します。
「マネックスの保険買取」は、マネックスグループ株式会社(東証プライム上場)の100%子会社であるマネックスライフセトルメント株式会社が運営する、生命保険の生前買取サービスです。
ご相談・査定は無料です。無理な勧誘は一切ございません
▼この記事の監修者

東京大学医学部医学科卒業。
<保有資格>
日本呼吸器学会認定呼吸器内科専門医
日本内科学会認定総合内科専門医
肺がんとは?原因と症状を解説
肺がんは、肺の中にある気管支や肺胞などの細胞が異常な増殖をはじめ、腫瘍となる病気です。肺がんは、がん細胞の種類によっていくつかのタイプに分類されます。
代表的な組織型は、腺がん、扁平上皮がん、大細胞がん、小細胞がんの4つです。このうち、最も多いのが腺がんで、肺がん全体の半数以上を占めます。
肺がんの原因や症状について詳しく見ていきましょう。
肺がんの原因
肺がんは、肺にある正常な細胞の遺伝子に傷がつき、その結果として異常な増殖が起こることで発症します。遺伝子の損傷を引き起こす原因はさまざまですが、最も大きな影響を与えるとされているのが「たばこ」です。
たばこを吸っている人は、吸わない人に比べて、男性で約4.8倍、女性で約3.9倍も肺がんを発症する確率が高いとされています。
たばこ以外にも、アルミニウムの粉じん、ヒ素を含む化合物、建築資材などに含まれるアスベスト(石綿)といった物質に長期的にさらされることでも、肺の細胞にダメージが蓄積され、がんの発症につながることがあります。
・山本康博先生より
たばこは肺がんの最大のリスク因子ですが、非喫煙者でも発症するケースはあります。とくに女性の腺がんや、職業的曝露歴のある方は注意が必要です。健康診断や画像検査を通じて、早期発見の意識を持つことが重要です。
参考: 日本医師会「肺がん検診 肺がんの原因」
肺がんの症状
肺がんは、早期にはほとんど自覚症状が現れないことも少なくありません。がんがある程度進行すると、咳(せき)や痰(たん)、血痰(けったん)、胸の痛み、発熱、息切れなどが現れる場合があります。
ただし、これらの症状は肺がん特有のものではなく、風邪や気管支炎、肺炎などの呼吸器の病気でも同様に見られることがあります。そのため、「咳が出るから肺がんだ」「熱があるからがんかもしれない」とすぐに決めつける必要はありませんが、逆に「たいしたことはない」と放置してしまうのも危険です。
とくに、いつもと違う咳が続く、血の混じった痰が出る、微熱が長引くなど、気になる症状が続く場合には、早めに医療機関を受診することが大切です。
肺がんの各ステージの状態と余命・生存率

肺がんには「小細胞肺がん」と「非小細胞肺がん」の2種類があります。
非小細胞肺がんには、以下の3種類があります。
- 腺がん:肺野(肺の末梢)に多く発生し、肺がんの中で最も頻度が高い。
- 扁平上皮がん:主に肺門(肺の中心部)に発生し、喫煙との関連が強い。咳や血痰などの症状が出やすい。
- 大細胞がん:肺野に多く見られ、増殖が速い。
小細胞肺がんは、肺門と肺野のどちらにも発生しやすく、進行が非常に速いのが特徴です。転移しやすく、喫煙との関連も大きいとされています。
各ステージの定義や余命・生存率についても異なります。
小細胞肺がんのネット・サバイバルは11.5%、非小細胞肺がんは47.5%です。ネット・サバイバルは期待生存率ではなく、純粋に「がんのみが死因となる状況」を仮定して算出する純生存率のことです。
肺がんの進行の程度は「ステージ(病期)」として分類され、I期(ステージ1)・II期(ステージ2)・III期(ステージ3)・IV期(ステージ4)と進むにつれて、がんの進行度が高くなります。
ステージの判定は、原発巣の大きさや広がり(T分類)、リンパ節転移の有無(N分類)、遠隔転移の有無(M分類)の3つの要素(TNM分類)を基に決定されます。
ここでは、肺がんのステージ別の生存率を解説します。
出典: がん情報サービス「院内がん登録生存率最新集計値」
肺がんステージ0(0期)
ステージ0(0期)は、肺がんの最も早期の段階にあたります。肺の粘膜内にとどまり、他の組織へ広がっていない状態です。医学的には「Tis(上皮内がん)」と分類され、がん細胞の充実成分がほとんど見られず、がんの大きさも3cm以下と極めて小さい特徴があります。
肺がんステージ1(I期)
ステージ1の肺がんは、がんの大きさが4cm以下であり、リンパ節転移が認められず、遠隔転移もない状態を指します。
ネット・サバイバルは、小細胞肺がんで43.2%、非小細胞肺がんで82.2%と報告されています。
肺がんステージ2(II期)
ステージ2の肺がんは、がんの大きさが4cmを超え7cm以下、またはリンパ節転移(※N1)が見られる状態を指します。
ネット・サバイバルは、小細胞肺がんで28.5%、非小細胞肺がんで52.6%とされています。
※NI:肺がんと同じ側の気管支周囲かつ・または同側肺門、肺内リンパ節への転移で原発腫瘍の直接浸潤を含める
参照: がん情報サービス「肺がん 非小細胞肺がん 治療」
肺がんステージ3(Ⅲ期)
ステージ3の肺がんは、がんの大きさが7cmを超える場合、あるいはリンパ節転移が特定の部位(※N2・N3)に及んでいる状態を指します。
ネット・サバイバルは、小細胞肺がんで17.5%、非小細胞肺がんで30.4%と報告されています。
※N2:同側縦隔かつ/または気管分岐下リンパ節への転移がある
※N3:がんがある肺と反対側の縦隔、対側肺門、同側あるいは対側の前斜角筋、鎖骨の上あたりにあるリンパ節への転移がある
参照: がん情報サービス「肺がん 非小細胞肺がん 治療」
肺がんステージ4(Ⅳ期)
ステージ4の肺がんは、がんが肺以外の臓器に転移している状態を指します。転移の状態に応じて下記に分類されます。
- M1a:肺がんがある反対側の離れたところに腫瘍がある、胸膜または心膜への転移、悪性胸水がある、悪性心嚢水がある
- M1b:肺以外の臓器への転移が1つのみ
- M1c:肺以外の1つの臓器または複数の臓器へ複数の転移がある
参照: がん情報サービス「肺がん 非小細胞肺がん 治療」
ネット・サバイバルは、小細胞肺がんで2.2%、非小細胞肺がんで9.0%です。
手術ができない肺がんのケース
肺がんの治療では、がんが肺の限られた範囲にとどまっている場合、手術による切除が可能です。しかし、進行の程度によっては手術が適応できないケースもあります。手術ができない肺がんとは、がんが進行しすぎている、または手術に耐えられない健康状態の場合を指します。
手術が適応できない場合、化学療法や放射線治療、免疫療法が中心となりますが、生存率は手術が可能なケースと比べて低くなります。
小細胞肺がんは進行が速く、診断時にはすでに広範囲に転移していることが多いため、手術が適応されるケースは限られます。
手術ができない小細胞肺がんのネット・サバイバルは8.4%、非小細胞肺がんは15.7%です。
出典: がん情報サービス「院内がん登録生存率最新集計値」
肺がんの治療法

肺がんの治療法には、手術や薬物療法などがあります。それぞれ詳しく見ていきましょう。
手術治療
手術は、がんを含む肺の一部や、がんが広がった周囲の組織を切除することで病巣を取り除く治療法です。
非小細胞肺がんでは、がんが局所にとどまっているⅠ期・Ⅱ期および一部のⅢ期の方に対して、根治を目的として行います。
手術の方法には、大きく分けて開胸手術と胸腔鏡手術の2種類があります。開胸手術は、胸の皮膚を15~20cm程度切開し、肋骨の間を広げて行う方法です。
一方、胸腔鏡手術は、数ヶ所の小さな切開部から胸腔鏡(細い棒状のカメラ)を挿入し、モニターに映し出される映像を見ながらがんを切除する方法です。近年では、手術支援ロボットを用いたロボット支援肺切除も導入されています。
小細胞肺がんの手術は、がんが比較的早期であるⅠ期・ⅡA期に限られます。通常、手術後には薬物療法(化学療法)を組み合わせて治療を継続します。
小細胞肺がんにおいても、手術の方法として開胸手術や胸腔鏡手術が選択されることが一般的ですが、最近では、皮膚の切開を8cm以下に抑えたハイブリッド胸腔鏡手術も取り入れられています。
放射線治療
放射線治療は、がん細胞を破壊する目的で高エネルギーの放射線を照射する治療法であり、がんの進行を抑えたり、症状を緩和したりする効果が期待されます。手術が困難な方や、病状の進行度合いによっては放射線治療が第一選択となることもあります。
非小細胞肺がんでは、主に切除できないⅢ期の進行がんに対して放射線治療が実施されます。場合によっては、化学放射線療法として薬物療法を組み合わせます。
ただし、化学放射線療法は、単独の放射線治療や薬物療法と比べて、副作用の発現率が高まることが報告されています。
小細胞肺がんにおいては、限局型の方が放射線治療の対象です。非小細胞肺がんの場合と同様に、化学放射線療法として同時に薬物療法を組み合わせる場合があります。
放射線治療では、治療期間中に下記のような副作用が現れます。
- 咳
- 皮膚炎
- 白血球の減少
- 貧血
- 食道の炎症 など
通常、治療が終了すると時間とともに改善することがほとんどですが、重症化するケースや治療後数ヶ月~数年が経過してから副作用が現れるケースもあるため、体調の変化に注意することが重要です。
薬物療法(抗がん剤)
薬物療法は、薬の力を用いてがん細胞の増殖を抑えたり、がんの進行を遅らせたりする治療法です。
非小細胞肺がんと小細胞肺がんのいずれにも適用されますが、それぞれのがんの性質に応じた異なる薬剤を使用します。非小細胞肺がんでは、「細胞障害性抗がん薬」「分子標的治療薬」「免疫チェックポイント阻害薬」の3種類が主に用いられ、小細胞肺がんでは、進行の速さに対応するため、基本的に細胞障害性抗がん薬が中心です。
ただし、進展型の場合は、免疫チェックポイント阻害薬が併用されることもあります。
薬物療法による副作用は、使用する薬剤の種類によって異なり、個人差も大きいです。細胞障害性抗がん薬はがん細胞の増殖を抑える一方で、正常な細胞にも影響を与えることがあり、その結果としてさまざまな副作用が現れます。
主な副作用は、脱毛や口内炎、下痢、白血球や血小板の減少などです。
分子標的治療薬は、がん細胞の増殖に関わる特定のタンパク質を標的として作用するため、正常細胞への影響は比較的少ないとされています。しかし、皮膚の発疹や肺高血圧症、肝機能障害といった副作用が現れることがあります。
免疫チェックポイント阻害薬は、免疫の働きを活性化させてがん細胞を攻撃する作用を持ちますが、その影響で自己免疫反応が強まることがあり、甲状腺機能異常や大腸炎、間質性肺炎などの症状が現れることがあります。
近年では、副作用を軽減するための対策も進んでおり、特に吐き気や嘔吐に対しては予防薬が使用されることで、治療中の負担を軽減できるようになってきています。
免疫療法
免疫療法は、私たちの体に備わっている免疫の仕組みを利用して、がん細胞を攻撃する治療法です。がん細胞は本来、体にとって異物であるにもかかわらず、巧妙に免疫の働きを抑える仕組みを持っているため、免疫細胞からの攻撃を逃れて増殖していきます。
免疫療法では、がん細胞による「免疫のブレーキ」を解除し、再び免疫細胞ががん細胞を認識し攻撃できるようにします。
日本において肺がん治療に有効とされている免疫療法は、「免疫チェックポイント阻害薬」と呼ばれる薬剤を用いた方法のみです。
末期の肺がん、手術ができない場合の選択肢
医師から「手術ができない末期の肺がんです」と伝えられたとき、多くの方が「これからどうすればいいのか」と不安を抱かれることでしょう。
手術ができないからといって治療の道が完全に閉ざされたわけではありません。状況に応じて選べる治療やサポートは複数あるため、本人と家族が納得できる形で日々を過ごすための選択肢を知ることが大切です。
ここでは、末期の肺がんと診断された方がとれる選択肢について紹介します。
・山本康博先生より
手術が適応とならない場合でも、薬物療法や放射線治療によりがんの進行を抑えることは可能です。近年では免疫療法の発展もあり、治療の選択肢は確実に広がっています。あきらめず、主治医とよく相談することが大切です。
最後まで治療を続ける
たとえ手術が適応でないと判断された肺がんであっても、薬物療法や放射線治療などの治療法によって、がんの進行を抑えたり症状を軽減したりすることは可能です。 主治医と相談を重ねることで、自分に合った治療法を模索することができます。また、現在受けている治療に疑問や不安がある場合は、他の専門医の意見を聞く「セカンドオピニオン」を活用することも有効です。
一方で、インターネットや口コミなどを通じて、さまざまな民間療法や高額な先進的な治療を知る機会もあるかもしれません。しかし、民間療法の中には科学的な根拠に乏しいものも多く、かえって健康を損なったり、高額な費用負担が発生したりするなどのリスクもあります。
ここで大切なのは、医学的根拠があるとされる「標準治療」が第一選択であることです。
先進医療に希望を感じる方もいるかもしれませんが、それが本当に必要なものかどうかは、専門医と相談した上で慎重に判断する必要があります。
緩和ケア(在宅・ホスピス)
治療を続けることが難しくなったときや、がんによる痛みや息苦しさ、不安といったつらい症状が強くなってきたときには、「緩和ケア」が選択肢になります。
緩和ケアは、がんの治癒を目指すものではなく、身体的・精神的な苦痛を和らげながら、その人らしい生活を送るための医療です。
緩和ケアには大きく分けて2つの方法があります。1つは、在宅医療を利用して自宅で過ごしながら受ける緩和ケアです。もう1つは、緩和ケア病棟(ホスピス)で医療スタッフのサポートを受けながら過ごす方法です。
在宅緩和ケアでは、家族に囲まれた慣れた環境で過ごすことができ、訪問診療や訪問看護が提供されます。ホスピスでは、医療スタッフによる手厚いケアのもとで痛みの緩和や心のケアを受けながら、穏やかな時間を大切に過ごせるよう配慮されています。
「マネックスの保険買取」は、マネックスグループ株式会社(東証プライム上場)の100%子会社であるマネックスライフセトルメント株式会社が運営する、生命保険の生前買取サービスです。
ご相談・査定は無料です。無理な勧誘は一切ございません
どちらの方法も、本人や家族の希望を尊重した形で選ぶことができます。治療を続けることだけが最良の選択とは限りません。自分がどう過ごしたいかを考え、希望に添ったサポートを受けることが大切です。
肺がんと診断されたら
肺がんの診断は、本人だけでなく家族にとっても大きな出来事です。手術が難しい、末期だと告げられても、治療の選択肢や生活の質を高める支援は残されています。医師とよく話し合いながら、自分らしい生き方を選んでいくことが大切です。不安なときには1人で抱え込まず、周囲のサポートや医療者の力を借りて、納得のいく選択をしていきましょう。
抗がん剤治療の費用はいくら必要?支払いに困った場合の対処法も解説

抗がん剤の治療は高くなりがちです。抗がん剤治療が必要になった場合、治療費をどのように準備すれば良いのでしょうか?この記事では、抗がん剤の治療費に不安を感じている方に、がんの治療にかかるお金の目安、治療費を抑える方法、抗がん剤治療費が払えないときの対処法について解説しています。
「マネックスの保険買取」は、マネックスグループ株式会社(東証プライム上場)の100%子会社であるマネックスライフセトルメント株式会社が運営する、生命保険の生前買取サービスです。
ご相談・査定は無料です。無理な勧誘は一切ございません
がんの治療にかかるお金
がんの治療費は「直接治療に必要な費用」と「治療以外に必要になる費用」に分けることができます。それぞれの費用について、細かく見ていきましょう。
治療に必要なお金
がんの代表的な治療法は「手術(外科治療)」「薬物療法」「放射線治療」の3つがあります。これらはどれか1つとは限らず、複数の治療法を組み合わせる場合もあります。
手術(外科治療)
腫瘍や臓器の悪い部分を取り除く治療のことです。臓器を切除したことで正常な機能を失う場合は、臓器同士をつなぎ合わせ、機能を回復させるための手術(再建手術)を行う場合があります。
がんが最初にできたところにとどまっている間は、手術でがんを取り除くことで治る可能性が高くなります。
薬物療法
薬でがん細胞を攻撃する方法で、「化学療法」「内分泌療法(ホルモン療法)」「分子標的療法」などの種類があります。
薬物療法はがんを直す、がんの進行を抑える、がんによる身体症状を緩和させるといった目的で行われます。
放射線治療
手術同様、局所に対する治療ですが、手術のように臓器を取り除くことなく、がんの部分に放射線をあてて治療します。放射線があたっても、痛みや熱を感じることはありません。
放射線治療は、大きく根治を目指す治療と、症状を緩和する治療があります。
治療以外のお金
がんに罹患すると、治療費以外にも交通費や入院時の消耗品、差額ベッド代などがかかります。また、がんで働けなくなったときに収入が減ることも考慮しなければなりません。
がんの治療以外にかかる費用についても、確認しておきましょう。
交通費
最近では薬物治療を通院で行うケースが増えています。治療のために公共交通機関やタクシーを使って通院する場合は、交通費がかかります。自家用車を使うにしても、ガソリン代がかかります。
家族の見舞いや付き添いにかかる交通費も考慮しておく必要があるでしょう。
入院時の消耗品
がんで入院しているときは、雑誌や着替え、有料テレビの視聴カード、飲料、スキンケアグッズなど何かと細かい出費があります。入院が長引けば出費がかさみ、意外に大きな支出になる可能性も考えられます。
差額ベッド代
入院の際に4床以下の病室を希望すると、差額ベッド代がかかります。差額ベッド代は全額自己負担になります。
がんで働けなくなったときの収入減
入院が長期化して仕事を休むと、収入が減少する可能性があります。お勤めの方は、公的医療保険から傷病手当金として、おおよそ給与の3分の2が支給されますが、それだけでは十分ではない方もいるかもしれません。
また個人事業主が加入する国民健康保険は、傷病手当金がないため、自身で収入を確保する方法を用意しておく必要があります。
・金子先生より
がんになると手術や入院以外にもお金がかかるため、がんと診断されたら一時金が受け取れる「がん診断一時金」に加入する方も多くいらっしゃいます。がんで入院や手術をしなければ受け取れないがん保険よりも、がんと診断されたら現金が受け取れるほうが便利に感じる方が多いようです。
がんになった時の治療費はいくらかかる?

がんになったら、どれくらいの治療費がかかるのでしょうか?厚生労働省の統計をもとに、治療費をがんの種類別にまとめました。またがんの治療の選択肢を広げるために、先進医療にかかる費用の目安も紹介しています。
癌の種類別の治療費を解説
がんの種類別の治療費と自己負担額は以下の通りです。
日本の公的医療制度では、原則かかった医療費の3割負担となるため、医療費総額の3割を自己負担として計算しています。
| がんの種類 | 入院 医療費総額 |
入院 自己負担 |
入院外 医療費総額 |
入院外 自己負担 |
合計 医療費総額 |
合計 自己負担 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 胃の悪性新生物 | ¥688,874 | ¥206,662 | ¥48,712 | ¥14,614 | ¥737,586 | ¥221,276 |
| 結腸の悪性新生物 | ¥679,963 | ¥203,989 | ¥45,082 | ¥13,525 | ¥725,045 | ¥217,514 |
| 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物 | ¥791,798 | ¥237,539 | ¥60,564 | ¥18,169 | ¥852,362 | ¥255,708 |
| 肝及び肝内胆管の悪性新生物 | ¥673,051 | ¥201,915 | ¥109,702 | ¥32,911 | ¥782,753 | ¥234,826 |
| 気管,気管支及び肺の悪性新生物 | ¥733,932 | ¥220,180 | ¥107,293 | ¥32,188 | ¥841,225 | ¥252,368 |
| 乳房の悪性新生物 | ¥618,330 | ¥185,499 | ¥58,599 | ¥17,580 | ¥676,929 | ¥203,079 |
| 子宮の悪性新生物 | ¥677,965 | ¥203,390 | ¥37,142 | ¥11,143 | ¥715,107 | ¥214,533 |
| 悪性リンパ腫 | ¥1,200,748 | ¥360,224 | ¥79,559 | ¥23,868 | ¥1,280,307 | ¥384,092 |
■参照:厚生労働省 令和4年度医療給付実態調査「性別、年齢階級別、疾病分類別、制度別、件数、日数(回数)、医療費 入院 (第4表の詳細版)」
悪性リンパ腫が他のがんに比べて医療費が高い傾向がありますが、入院中の医療費総額が約60~80万円、自己負担が約20万円前後となっています。
入院外の医療費総額は、がんの種類によってバラつきがありますが、医療費総額で約3~11万円、自己負担が約1~3万円前後となっています。
また近年では入院を伴わないがん治療が増えていますが、依然として、がんにかかる医療費は入院が大半を占めていることがわかります。
先進医療
がんの治療のなかには、健康保険の適用とならない治療もあります。
代表的な治療が「陽子線治療」と「重粒子線治療」です。これらの治療は、疾病によっては先進医療に該当し、健康保険の対象外となる場合があります。先進医療とは、高度な医療技術を用いた治療やその他の療養のうち、公的医療保険の対象とすべきか検討中の療養のことです。
先進医療はその技術の有効性や安全性を確保するため、医療技術ごとに、治療を受けられる医療機関が限られています。なおかつ先進医療にかかる技術料は、すべて自己負担となります。
厚生労働省「令和5年6月30日時点における先進医療に係る費用」のデータから、陽子線治療1件あたりの自己負担額が約266万円、重粒子線治療が約314万円であることがわかります。
公的医療保険の治療のみでがんの治療ができるのであれば、それに越したことはありません。しかし日々医療技術は進歩しており、先進医療を選んだほうが良いケースもあるでしょう。治療の選択肢を広げるためにも、高額な治療をするための費用も準備しておきたいところです。
治療費を抑える公的サービスを活用する
抗がん剤治療が高額になった場合、高額療養費制度を利用すれば自己負担を抑えられます。また医療費が高額になったときは、確定申告で医療費控除を受けることで、支払った税金が還付または軽減され、実質的に医療費負担を減らせる場合があります。
抗がん剤治療は高額医療費制度の対象になる?
抗がん剤の治療費は、抗がん剤の種類や投与量で決まりますが、高額になりがちです。高額になったときのために、高額療養費制度の自己負担限度額を確認しておきましょう。
高額療養費制度とは、同一月に医療費の自己負担が上限を超えた場合、超えた分について払い戻しを受けられる制度です。自己負担額の上限は、年齢や所得で異なります。
自己負担の上限と高額療養費としていくら払い戻されるのか、70歳未満で年収400万円の人がステージ1の胃癌で20日入院し、1日の入院費用が「79,715円」と仮定した場合で計算してみましょう。
70歳未満、年収400万円の場合、自己負担限度額は以下の計算式で計算をします。
自己負担限度額=80,100円+(医療費-267,000円)×1%
【計算例】
- 1日あたりの入院費用: 79,715円 × 20日間 = 1,594,300円(1ヶ月にかかった医療費)
- 自己負担上限額: 80,100円 + (1,594,300円 - 267,000円) × 1% = 93,373円
- 窓口負担: 1,594,300円 × 30%(3割負担) = 478,290円
- 払い戻される金額: 478,290円 - 93,373円 = 384,917円
高額療養費制度は一旦医療費を全額立て替えて支払い、後で自己負担限度額を超えた分が、約3ヶ月後に払い戻される仕組みです。
ただし「限度額適用認定証」を病院や薬局の窓口に提出するか、マイナ保険証で受診すると、立て替え払いが不要になります。
医療費控除で治療費を実質的に抑える
医療費控除とは、1月1日~12月31日の間に、納税者本人と、納税者と生計を一つにする親族が支払った医療費が10万円を超える場合、確定申告をすることで受けられる控除です。
医療費控除を受けることで、所得税・住民税が還付または軽減されるため、実質的に治療費を抑えられます。
医療費控除の対象となる費用は、治療費や入院費、通院費だけでなく、治療や療養に必要な医薬品の購入費や医師の送迎費、義手や補聴器などの購入費、医療用器具の購入費やレンタル費用などがあります。
年収400万円で東京在住、40歳未満の会社員が、胃がんで年間20万円の治療費の自己負担が生じた場合で、医療費控除が適用になるとどれくらい所得税が還付(軽減)されるか計算してみましょう。
なお、医療費控除以外に適用される控除は、給与所得控除と社会保険料控除、基礎控除のみとします。
医療費控除額は以下の計算式を用いて計算します。
医療費の合計額-保険金などで補てんされる金額-10万円または、年間所得金額の5%のうちいずれか少ないほう※
※1年間の所得が200万円未満の場合は、所得の5%となります。
年収400万円で東京都在住、40歳未満の会社員の場合、給与所得控除額は124万円、基礎控除は48万円、社会保険料控除は約58万円なので所得税を計算するときの基礎となる、課税所得金額は400万円-124万円-48万円-58万円=170万円です。
このケースでは所得税率が5%なので、年間所得税額は170万円×5%=約8.5万円となります。
さらに年間20万円の治療費がある場合、このケースでは以下の計算で医療費控除額を計算します。
医療費控除額は、20万円-0円(保険金などで補填される金額なし)-10万円※=10万円です。
この医療費控除を考慮して所得税額を計算すると、(170万円-10万円万円)×5%=8万円となるため、5,000円の還付が受けられます。つまり5,000円分、所得税が軽減されたことになります。
※給与所得276万円×5%>10万円のため
・金子先生より
医療費控除は納税者本人だけでなく、納税者と生計を一つにする親族が支払った医療費も対象になります。自身の医療費だけでは医療費控除が利用できなくても、親族の医療費を合計すれば利用できるかもしれないため、一度、家族の医療費を洗い出してみましょう。
抗がん剤治療費用が払えない場合の対処法とは?

抗がん剤治療の費用が支払えないときは、病院に分割払いや支払いの延期ができないか相談してみましょう。その他、公的サービスを利用する方法や医療ローン、生命保険買取サービスを利用する方法についても紹介します。
病院に相談してみる
抗がん剤の治療代を支払えないときは、分割払いや支払いの延期を認めてもらえるケースがあるため、病院や病院のソーシャルワーカーに相談してみましょう。無料定額診療事業や生活保護などの公的支援制度を紹介してもらえる場合もあります。
無料低額診療事業とは、低所得者などに、医療機関が無料あるいは低額な料金で診療を行う事業です。生活保護制度とは、世帯の収入だけでは、国が定める最低生活費に満たない場合に、生活費の支給を受けられる制度を指します。
高額療養費貸付制度
高額療養費として払い戻される予定金額の8割(協会けんぽの場合)、無利子で貸し付ける制度です。
高額療養費制度は、自己負担を超えた分が約3ヶ月後に払い戻されますが、一旦医療費を全額立て替えなければなりません。
しかし高額療養費貸付制度で借りることができれば、高額療養費の立て替え払いの負担が軽減されます。
貸付金の返還は、後日支給される高額療養費を充てるため、実質、高額療養費の払い戻しを早めに受けられる制度と言えるでしょう。
高額療養費制度は、協会けんぽや国民健康保険、会社の健康保険で取り扱っています。
医療ローン
医療関連の支払い全般に充てられる、医療ローンを利用する方法もあります。健康保険が適用されない治療を受け、自己負担が高額になったときにも利用できます。
医療ローンは、主に銀行や信販会社などの金融機関で扱っています。医療ローンを利用するには、金融機関の審査に通過しなければなりません。
銀行の審査では返済能力が重視されるため、審査は厳しめで、審査期間も数日~1週間と長い傾向があります。
信販会社の医療ローンは、病院やクリニックから紹介されるのが一般的です。銀行よりも金利が高めですが、審査にかかる時間が短く、数時間から数日で利用できます。
医療ローンは、お金の使い道が医療関連の支払いに限定されているため、資金使途を問わないカードローンよりも低い金利で利用できる点もメリットと言えます。
生命保険の売却も選択肢の1つ
生命保険買取サービスで自身が加入している生命保険を売却し、受け取ったお金で抗がん剤の治療費を支払う方法もあります。
生命保険を売却してお金を受け取った後は、生命保険の買取会社(以降、買取会社)が保険料を支払い、保険の被保険者に万が一のことがあったときは、保険金を買取会社が受け取る仕組みです。
マネックスの保険買取サービスは、がん患者の保険契約のみ買い取りをしています。買取金額は、罹患したがんの種類や現在のステージ、年齢・性別、保険金額、保険料などで異なりますが、解約返戻金よりも高い金額で買い取ってもらえる可能性があります。
保険を売却することでまとまったお金が受け取れるため、がんの治療費や生活費が不安な方、保険料の負担が難しくなった方にも便利なサービスです。
がんの治療費に困ったらまず相談
がんの治療費は高額になる場合もあるため、治療費の支払いに困ったり、不安を感じたりしたら、まず病院やソーシャルワーカーに相談することが大切です。
治療費の負担を軽減する公的サービスや、医療ローン、生命保険買取サービスなど、がんの治療費の支払いをサポートするサービスもあるため、各サービスの仕組みも確認しておきましょう。
「マネックスの保険買取」は、マネックスグループ株式会社(東証プライム上場)の100%子会社であるマネックスライフセトルメント株式会社が運営する、生命保険の生前買取サービスです。
ご相談・査定は無料です。無理な勧誘は一切ございません
▼この記事の監修者
 金子賢司(かねこ けんじ)
金子賢司(かねこ けんじ)
東証一部上場企業勤務、ファイナンシャルプランナー金融に興味を持ち、資産運用やローンなどの勉強を始める。以降ファイナンシャルプランナーとして活動し、個人・法人のお金に関する相談、北海道のテレビ番組のコメンテーター、年間毎年約100件のセミナー講師を務める。趣味はフィットネス。健康とお金、豊かなライフスタイルを実践・発信しています。
<保有資格>CFP、損保プランナー、生命保険協会認定FP
がんになったら払わなくていいお金・もらえるお金を解説

がんになると高額な治療費がかかるため、経済的な不安を抱えてしまうかも知れません。この記事では、がんの治療費を軽減する制度や、経済的なサポートを受けられる制度について分かりやすく解説しています。
「マネックスの保険買取」は、マネックスグループ株式会社(東証プライム上場)の100%子会社であるマネックスライフセトルメント株式会社が運営する、生命保険の生前買取サービスです。
ご相談・査定は無料です。無理な勧誘は一切ございません
がんになったら払わなくいいお金
がんになって医療費が高額になると、高額療養費制度や医療費控除により、自己負担が軽減される場合があります。また収入が減少した場合、国民健康保険や国民年金の保険料の負担が軽減されます。
住宅ローンを利用している方は、加入している団体信用生命保険の内容によっては、住宅ローンの残債がゼロになる場合もあるため、保障内容を確認してみましょう。
ここでは、がんになったら払わなくていいお金について紹介します。一部の医療費
医療費は原則3割負担ですが、月の医療費が一定額を超えると、高額療養費制度が適用され、さらに医療費の自己負担が軽減されます。
高額療養費制度とは、同一月に医療費の自己負担が上限を超えた場合、超えた分について払い戻しを受けられる制度です。自己負担額の上限は、年齢や所得によって異なります。
【高額療養費制度の自己負担上限額の計算式の一例】
69歳以下、年収約370~約770万円の場合
80,100円+(医療費-267,000円)×1%=自己負担上限額
制度を利用するときの連絡先は、加入している医療保険制度の運営元によって異なります。
例えば中小企業にお勤めの方が高額療養費制度について問い合わせるときは、管轄の全国健康保険協会の支部に連絡をします。
【高額療養費制度の問い合わせ先】
| 運営元 | 主な被保険者(保険の対象となる人) | 問い合わせ先 |
|---|---|---|
| 健康保険組合 | 大企業など民間企業の従業員 | 各健康保険組合の窓口 |
| 全国健康保険協会(協会けんぽ) | 中小企業の従業員 | 協会の各都道府県支部 |
| 国民健康保険 | 自営業者やフリーランス | 市区町村役所(場)の担当窓口 |
| 共済組合 | 公務員や私立学校の職員 | 各共済組合担当窓口 |
高額療養費制度は、一旦自身で医療費を全額立て替えて、自己負担限度額を超えた分が約3ヶ月に払い戻される仕組みです。
ただし病院や薬局の窓口に「限度額適用認定証」を提出するか、マイナ保険証で受診すると、立替払いが不要になります。
税金の一部
確定申告のときに医療費控除の手続きをすることで、税金が還付または軽減されます。
医療費控除とは、1月1日~12月31日の間に、納税者本人と、納税者と生計を一つにする親族が支払った医療費が10万円を超える場合に利用できる控除のことです。
医療費控除の計算は以下の計算式で計算をします。
医療費控除額(最高200万円)=1年間(1月~12月)に支払った医療費-保険金などで補填された金額-10万円または所得総額5%のどちらか少ない方
ケガや病気の診療費や治療費、入院費の他、医薬品の購入費や、病室の部屋代、医療用器具の購入費やレンタル費用、通院のために支払った交通費なども医療費控除の対象になります。
また健康保険が適用されない先進医療の技術料や、疾病の治療にともなうものであれば自由診療も医療費控除の対象となります。
医療費控除を受けるためには、以下の4つの手順で進めていきます。
- 医療通知書や領収書などの証票を集める
- 確定申告書と医療費控除の明細書を作成
- 税務署に申告
- 還付金の確認(還付を受ける場合)
確定申告は2月16日から3月15日の間に、前年の1月1日から12月31日までの間の所得に対する税金を計算します。
確定申告をするときは、まず前年1年間の医療費の総額を確認してみましょう。医療費総額が10万円以上、または総所得金額の5%のいずれか低い方の金額を上回っていれば医療費控除を受けられる可能性があります。毎年2月半ばころに運営元から送られてくる医療通知書を確認するとスムーズです。
医療費控除を受けられる可能性があるときは、税務署の窓口や、国税庁のWebサイトから、確定申告書と医療費控除の明細書を入手して、必要項目に記載のうえ管轄の税務署に提出します。オンライン納税システム「e-Tax」を利用すれば、パソコンやスマートフォンからの申告も可能です。
国民健康保険・国民年金の保険料納付免除
がんで働けなくなった場合、国民健康保険の保険料を軽減できる場合があります。国民健康保険は主に、個人事業主やフリーランスが加入する健康保険制度です。
国民健康保険は、災害やその他の事情で国民健康保険料を納めることが困難な場合、申請をすることで、保険料の減免や納税猶予を受けられる場合があります。まずは自身が住んでいる市町村の国民健康窓口に問い合わせてみましょう。
また個人事業主や専業主婦の他、がんの治療で会社を退職した方は国民年金の被保険者ですが、がんによる失業などで国民年金の支払いが困難なとき、申請により保険料の一部または全部が免除となります。年金は原則65歳から受け取りが可能ですが、年金を受け取るためには、保険料納付済期間が10年以上なければなりません。免除であれば、その期間も年金額に反映されますが、未納の場合は反映されないため注意が必要です。
保険料免除期間中に、所定の障害状態になったときや死亡した場合、所定の要件を満たしていれば障害年金や遺族年金も受け取れます。国民年金の「免除」と「未納」は大きく異なります。
国民年金保険料の支払いが難しいときは、住所地の市区役所、町村役場の国見年金窓口に相談しましょう。手続きは、デジタル庁のオンラインサービスである、マイナポータルを利用した電子申請も可能です。
住宅ローンの支払い免除
住宅ローンを組むときに加入する団体信用生命保険(以下、団信)の内容次第では、がんになると住宅ローンの支払いが免除される場合があります。
団体信用生命保険とは、住宅ローンの返済期間中、債務者に万が一のことがあると残債がゼロになる保険です。団信のなかには、死亡・高度障害状態だけでなく、債務者ががんになったときも残債がゼロになるタイプもあります。がんも保障対象になる団信に加入していれば、がんになった場合、住宅ローンの残性がゼロになり自宅も手元に残せます。
がんで働けなくなった場合にもらえるお金
がんで働けず収入が減少した場合、傷病手当金が受け取れる場合があります。また働ける状態になって求職している期間中は、雇用保険の基本手当を受け取ることも可能です。生活費や医療費の負担が大きく、生活が厳しくなったときは、生活保護制度が利用できる場合があります。
傷病手当金
がんで働けなくなり、給料が支払われなくなったり、減額されたりしたときに給付される手当金です。なお、国民健康保険には傷病手当金の制度がありません。
傷病手当金の給付要件は以下の通りです。
- 業務外の病気やケガであること
- 療養のため業務ができないこと
- 就労不能の日が3日以上連続していること
- 給与の支払いがない、または減額されていること
傷病手当金は、業務外の病気やケガの療養で業務ができない日が、3日以上連続していることが要件です。業務ができないかどうかの判断は、医師の意見や被保険者の業務内容などを考慮して判断されます。給与が一部でも支給されているときは、傷病手当金から給与支給分を差し引いた金額が支払われます。
受給できる期間は、同一の傷病であれば、受給が始まった日から通算して1年6ヶ月です。受給金額は、以下の計算式で計算をします。
1日あたりの傷病手当金=直近12ヶ月分の標準報酬月額の平均額÷30×2/3
標準報酬月額とは、1ヶ月あたりの給料を1~50等級に分類したもので、厚生年金保険料や健康保険料を計算するときにも利用されます。
なお支給額や支給期間は、健康保険組合によっては上乗せしている場合もあります。
また傷病手当金申請の流れは以下の通りです。
- 傷病手当金支給申請書に必要事項を記入、押印
- 医師に診断書をもらう
- 傷病手当金支給申請書に診断書を添えて、健康保険組合や協会けんぽに提出
申請書と診断書を提出した後、審査に問題がなければ、一般的に申請日の2週間~1ヶ月後に振り込まれます。なお、支給日が毎月10日、20日、末日など決まっている場合もあります。
・金子さんより
個人事業主やフリーランスが加入する国民健康保険は、傷病手当金の仕組みがありません。そのためケガや病気で働けなくなり、収入が減ったときのリスクは、お勤めの方よりも大きくなります。生命保険会社で扱っている就業不能保険や、損害保険会社であつかっている所得補償保険等も検討しましょう。
基本手当(雇用保険)
がんで働けなくなり、再度働けるようになっているにもかかわらず、就職ができない期間中は雇用保険による基本手当が受け取れます。
雇用保険の基本手当の受給要件は以下の通りです。
- ハローワークに来所して求職の申し込みをしている
- いつでも就業できる能力があること
- 積極的に就職しようとしている意思があること
- 離職の日以前2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して12ヶ月以上あること
がんの治療中は、いつでも就業できる能力があると認められません。基本手当の受給期間は離職の日の翌日から1年間に限られているため、がんの治療で受給期間が過ぎてしまうと、基本手当が受け取れなくなってしまいます。
離職日の翌日から1年以内に30日以上継続して働けないときは、延長申請により本来の受給期間である1年に働けない日数を加えることができ、再度、働ける状態になった後に、受給手続きができます。
なお、受給期間に加えられる期間は最大3年間です。
基本手当が給付される日数は、離職理由や年齢で異なり、最長330日となっています。
また雇用保険の基本手当として受給できる1日あたりの金額は、原則、離職した日の直前の6ヶ月に毎月支払われた賃金(賞与などを除く)の合計を、180で割った金額の50~80%です。受給できる1日あたりの金額は、年齢に応じて7,065円~8,635円(令和6年8月1日現在)と上限が定められています。
雇用保険の基本手当を受け取るときの流れは、以下の通りです。
- 雇用保険被保険者離職票を用意する
- その他の必要書類(マイナンバーカード・証明写真2枚(縦3.0cm×横2.4cm)本人名義の通帳かキャッシュカード)を用意する
- ハローワークに求職の申し込みを行い、必要書類を提出
- 雇用保険受給者初回説明会に参加
- 失業の認定を受ける
- 雇用保険の給付
継続して基本手当を受け取るときは、指定された日に定期的にハローワークに行き、失業状態の認定を受ける必要があります。
生活保護
がんで収入が減少したり、医療費負担が増加したりして生活が困難になった場合、生活保護が利用できる場合があります。
生活保護を利用できる要件は、以下の通りです。
- 資産を保有していない
- 厚生労働省が定める基準で計算される最低生活費より収入が低い
- 親族から経済的な援助が受けられない
生活保護で支給される内容は、光熱費や食費、被服費といった日常生活に必要な費用を扶助する「生活扶助」や、家賃などを扶助する「家賃扶助」など、8種類の扶助から構成されています。
このうち医療扶助が適用されれば、がんの治療にかかる医療費が無料になります。ただし医療扶助は現金支給ではなく、自治体から発行される医療券を医療機関に提出する仕組みです。また医療券が利用できるのは、自治体によって指定された医療機関に限られます。
生活保護の利用を希望する方は、住んでいる地域を管轄する、福祉事務所の生活保護担当に相談をしましょう。生活保護の申請をした後、生活状況や資産、扶養親族からの仕送り状況、就労可能性などの調査が行われ、保護が必要と福祉事務所長が判断すれば、生活保護が受けられます。
生活保護を受給する場合、原則一定以上の資産が保有できないため、貯蓄性があるものや保険料が高い生命保険は解約が必要になるケースもあります。
保険の解約をするときは、解約返戻金よりも高い金額で買い取ってもらえる可能性がある、生命保険買い取りサービスの利用も検討してみましょう。
がんで障害が残った時にもらえるお金
がんの治療をして、障害が残った場合にも受け取れるお金があります。以下、障害年金と障害手当金について解説します。
障害年金
病気やけがで障害状態になったとき、障害年金が受け取れる場合があります。
障害年金は法令によって障害の程度が定められており、等級に応じて支給される障害年金額が異なる仕組みです。
支給される障害年金の金額(令和6年度)は以下の通りです。
初診日に国民年金の被保険者の方で所定の要件を満たしている方は、障害基礎年金が受け取れます。また初診日に厚生年金の被保険者で、障害等級1級、2級に該当する方は、障害基礎年金と障害厚生年金の両方が受け取れます。
| 障害等級 | 障害の程度 | 障害年金の金額 | その他の情報 |
|---|---|---|---|
| 障害等級1級 | 他人の介助を受けなければ、日常生活のことがほとんどできないほどの状態 | 1,020,000円 | +子の加算 報酬比例の年金×1.25倍+配偶者加給年金 |
| 障害等級2級 | 必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活は極めて困難で、労働で収入を得ることが難しいほどの障害 | 816,000円 | +子の加算 報酬比例の年金+配偶者加給年金 |
| 障害等級3級 | 労働が著しい制限を受ける、または、労働に著しい制限を加えることを必要とするような状態 | 報酬比例の年金(最低保証612,000円) |
【子の加算】
| 子の数 | 金額 |
|---|---|
| 1人目、2人目の子 | 1人につき234,800円 |
| 3人目以降の子 | 1人につき78,300円 |
がんに関連する、主な治療の認定基準を紹介します。
| 治療法 | 該当する障害等級 |
|---|---|
| 人工肛門の造設 | 原則3級、ただし新膀胱を造設したもの、または尿路変更術を施した場合など、2級以上に認定される場合もある |
| 喉頭全摘出 | そしゃく機能を欠くものは2級、そしゃく機能に相当程度の障害を残すものは3級 |
| 抗がん剤の副作用 | 副作用の状態に応じて1~3等級に分かれる |
障害年金を請求する場合、以下の流れで手続きを進めていきます。
- 初診日を調べる
- 年金事務所で保険料納付要件を満たしているか確認する
- 初診日が証明できる書類を揃える
- 医師に診断書を書いてもらう
- 病歴・就労状況など申立書を作成する
- 初診日時点で国民年金の方は、住所地の市区町村の国民年金課、お勤めだった方とその配偶者は年金事務所か街角の年金相談センター、公務員は所属していた共済組合で手続きを行う
障害手当金
がんで障害等級1~3等級に該当しない場合、障害手当金という一時金が受け取れる場合があります。障害手当金が受け取れるのは、初診日時点で厚生年金の被保険者だった方で、5年を経過するまでの間に、これ以上、治療の効果が期待できなくなった場合に限られます。
受け取れる障害手当金の金額は、令和6年の場合1,224,000円(昭和31年4月1日以前に生まれた方は1,220,600円)です。
手続きの方法は障害年金と同じです。
がんで介護が必要になったら知っておきたいこと

がんで介護が必要な状態になり、医療費と介護費を合算した金額が高額になったとき、高額介護合算療養費制度が利用できる場合があります。
また介護が必要なため休業する方は、介護休業給付金が受給できます。
以下、がんで介護が必要になったときに知っておきたい制度について見ていきましょう。
高額介護合算療養費制度
がんの影響で介護が必要になる可能性もあります。介護保険は65歳以上の方だけでなく、16種類の特定疾病が原因で介護を必要とする状態になった場合、介護保険が利用できます。
毎年8月から1年間にかかった医療保険と介護保険を合計して、自己負担額が著しく高額になった場合、高額介護合算療養費制度を利用することで、負担額の一部が払い戻されます。
高額介護合算療養費制度を利用するための要件は以下の通りです。
- 国民健康保険、健康保険、後期高齢者医療制度の各医療保険における世帯内であること
- 1年間の医療保険と介護保険を合計した自己負担額が、各所得区分に設定された限度額を超えた世帯であること
【自己負担限度額(70歳未満)】
| 月給・所得 | 限度額 |
|---|---|
| 月給:81万円以上 所得:901万円超 |
212万円 |
| 月給:51.5万円以上81万円未満 所得:600万円超901万円以下 |
141万円 |
| 月給:27万円以上51.5万円未満 所得:210万円超600万円以下 |
67万円 |
| 月給:27万円未満 所得:210万円以下 |
60万円 |
| 住民税非課税者 | 34万円 |
高額介護合算療養費制度を利用するときの窓口は、各市区町村役場の介護保険、加入する医療保険(国民健康保険や健康保険組合など)となります。
介護休業給付金
対象となる家族を介護するために休業し、給与が支払われなかったり減額されたりした場合は、介護休業給付金が給付されます。
【対象となる家族】
- 配偶者・父母・子・配偶者の父母
- 同居かつ扶養している祖父母・兄弟姉妹・孫
【介護休業給付金を受給するための要件】
- 介護休業開始前2年間に11日以上就業した月が12ヶ月以上
- 介護休業中に仕事をした月が、月に10日以下
- 介護休業中の毎月の賃金が、休業前の80%未満
- 対象となる家族が2週間以上にわたり常時介護が必要な状態
受け取れる金額は以下の計算式で計算をします。
介護休業給付金の給付額=賃金(日額)×支給日数×67%
会社からの給与が13%~80%の場合は80%までの差額、80%を超える場合は支給されません。
手続きは、勤務している方は勤務先を通じて、本人が行う場合はハローワークで手続きを行います。
まとめ
がんになると治療費だけでなく、働けなくなり、収入が減少するリスクにも備えなければなりません。しかし、がんになって払わなくてよくなるお金や、働けなくなったときの収入をサポートする制度も用意されています。少しでもがんの不安を軽減するために、こうした制度の受給要件や手続き方法を確認しておきましょう。
「マネックスの保険買取」は、マネックスグループ株式会社(東証プライム上場)の100%子会社であるマネックスライフセトルメント株式会社が運営する、生命保険の生前買取サービスです。
ご相談・査定は無料です。無理な勧誘は一切ございません
▼この記事の監修者
 金子賢司(かねこ けんじ)
金子賢司(かねこ けんじ)
東証一部上場企業勤務、ファイナンシャルプランナー金融に興味を持ち、資産運用やローンなどの勉強を始める。以降ファイナンシャルプランナーとして活動し、個人・法人のお金に関する相談、北海道のテレビ番組のコメンテーター、年間毎年約100件のセミナー講師を務める。趣味はフィットネス。健康とお金、豊かなライフスタイルを実践・発信しています。
<保有資格>CFP、損保プランナー、生命保険協会認定FP
胃がんのステージ別の余命・生存率とは?胃がんの原因や症状も解説

胃がんは、早期発見・早期治療により、余命・生存率の向上が期待できます。しかし、進行するほど治療が難しくなり、余命も短くなる傾向があります。本記事では、胃がんの原因や症状、各ステージの状態と生存率について詳しく解説します。
「マネックスの保険買取」は、マネックスグループ株式会社(東証プライム上場)の100%子会社であるマネックスライフセトルメント株式会社が運営する、生命保険の生前買取サービスです。
ご相談・査定は無料です。無理な勧誘は一切ございません
胃がんとは?原因と症状を解説
胃がんは、胃の内壁を覆う粘膜にできるがんです。進行するにつれて、粘膜から粘膜下層、固有筋層、漿膜(しょうまく)と外側へ広がっていき、最終的には周囲の臓器やリンパ節に転移します。
胃がんの原因と症状について詳しく見ていきましょう。
胃がんの原因
胃がんの原因として、さまざまな要因が考えられています。その中でも特に重要とされるのが、ヘリコバクター・ピロリ菌感染、食生活、生活習慣です。長期にわたって胃の健康に影響を与え、胃がん発症のリスクを高める要因とされています。
まず、ヘリコバクター・ピロリ菌は胃の粘膜に感染し、慢性の炎症を引き起こします。炎症が続くことで胃粘膜がダメージを受け、胃がんの発生リスクが増加します。ヘリコバクター・ピロリ菌の除菌治療によってリスクを軽減できることもあるため、検査で感染が確認された場合は医師と相談のうえ除菌治療を検討しましょう。
次に、食生活も胃がんの発症に深く関わっています。塩分の多い食品は胃の粘膜にダメージを与えるため、胃がんのリスクを高める原因となります。漬物や塩辛、味噌など塩分の高い食品は日本人が好んで食べる傾向があるため、場合によっては食生活の見直しが必要です。
また、野菜や果物の摂取が不足すると、胃粘膜が十分に保護されず、胃がんのリスクが高まります。
生活習慣については、中でも喫煙が胃がんに関わるとされています。タバコに含まれる有害物質が胃の防御機能を低下させ、胃がんのリスクを高めます。さらに、過度な飲酒も、アルコールが胃の粘膜を刺激し、炎症を引き起こすことから胃がんのリスク要因です。
胃がんの症状
胃がんは、早期段階では自覚症状がほとんどなく、症状が現れた時にはがんが進行しているケースが多いです。胃がんの症状は、胃潰瘍や胃炎など他の消化器疾患と似ているため、症状が出てもすぐに胃がんだと判断するのは難しいとされています。
胃がんで見られる主な症状について、詳しく見ていきましょう。
食欲不振
胃がんが進行すると、胃の機能が低下し、消化不良や満腹感が常にみられるようになります。その結果、食欲が減少することがあります。
胃痛や不快感
胃がんが胃の内壁から外側へ浸潤するにつれて、痛みや不快感が現れることがあります。胃潰瘍や胃炎の痛みと似ているため、診断が遅れることも少なくありません。
胃もたれ・胸やけ
胃がんにより胃の消化機能が低下すると、胃もたれや胸やけが頻繁に起こるようになります。食事をした後に、胃がすっきりせず、消化不良が続く感じや、胸の辺りが焼けるような感覚を持つことがあります。
黒色便
胃がんが進行すると、がんが胃の壁を侵食し、内部で出血が発生することがあります。胃の中で出血が起こると、血液は消化器を通過し、便が黒色(タール状)になることがあります。黒色便が見られた場合は、胃がんの進行によるものかもしれないため、すぐに医療機関で診察を受ける必要があります。
体重減少
急激な体重減少は、胃がんが進行している場合の典型的な症状です。がんが胃の消化機能に影響を与えることで、栄養の吸収が阻害され、食事の量が減るだけでなく、体内の代謝が異常を起こすことで脂肪量や筋肉量が減少するために体重が減少します。
胃がんの各ステージの状態と生存率
胃がんの進行度はステージ(病期)によって分類され、各ステージごとに生存率が異なります。全症例の10年生存率は56.8%です。
純粋に「がんのみが死因となる状況」を仮定して計算する純生存率を「Net Survival(ネット・サバイバル)」といいます。
院内がん登録2011年10年生存率の報告では、がん診療連携拠点病院などの院内がん登録データを用いて、10年生存率を算出しました。
ステージ別の基準と生存率について、詳しく見ていきましょう。
出典:国立がん研究センター「院内がん登録2011年10年生存率集計 公表 小児がん、AYA世代のがんの10年生存率をがん種別に初集計」
胃がんステージ0(0期)
ステージ0は、がんが胃の最内層である粘膜層に留まっている状態です。この段階では、内視鏡治療で完全にがんを取り除くことができ、生存率も非常に高いとされています。
胃がんステージ1(I期)
ステージ1では、がんが粘膜層か粘膜下層に留まっている状態で、リンパ節への転移はありません。10年生存率は77.6%です。
胃がんステージ2(II期)
ステージ2は、がんが固有筋層まで進行しているか、少数のリンパ節に転移が見られる状態です。この段階でも治療の成功率は比較的高く、10年生存率は48.9%です。
胃がんステージ3(Ⅲ期)
ステージ3は、がんが固有筋層を完全に越え、漿膜下層へと浸潤している状態です。リンパ節に転移が見られます。10年生存率は32.0%です。
胃がんステージ4(Ⅳ期)
ステージ4は、他の臓器にがんが転移した状態です。腹水がたまる場合、余命は短いケースが多く、治療は緩和ケアが中心となります。10年生存率は5.9%です。
がんで腹水がたまってしまった時の余命
末期がんになると、がん細胞が腹膜に広がり、腹水がたまることがあります。これは進行がんの典型的な症状で、腹水がたまると食事摂取が難しくなり、栄養状態が悪化します。腹水が見られる場合、余命は通常数ヶ月から半年程度といわれています。
ただし、腹水は余命を明確に示すものではないため、腹水がたまった時点で近いうちに亡くなると決まっているわけではありません。
胃がんの治療法
胃がんの治療法は、がんの進行度や患者の体調に応じて選択されます。胃がんの治療法について詳しく見ていきましょう。
手術治療
手術治療は、胃がんが初期段階または局所に留まっている場合に効果的な治療法です。早期の胃がんでは、内視鏡を用いてがん細胞のみを切除する「内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)」を行える場合があります。体への負担が少なく、数日で退院することが可能です。
進行した胃がんに対しては、部分的な胃切除や、がんの広がりが大きい場合には胃全摘術を行います。たとえば、胃の出口付近にがんがある場合には、幽門側胃切除術という手術で胃の下部2/3を切除し、残った胃と十二指腸、または小腸をつなげます。また、がんがリンパ節に転移している可能性がある場合には、リンパ節郭清という周囲のリンパ節も同時に取り除く手術も行います。
・甲斐沼先生より
昨今、一部の早期がんに対して、内視鏡を使ってがんを切除することが行われています。
胃がんに対する内視鏡切除術には大きく2つの方法があり、EMR(正式名称:内視鏡的粘膜切除術)とESD(正式名称:内視鏡的粘膜下層剥離術)です。
従来は、EMRにて治療が行われていましたが、大きな病変だと分割切除になり、遺残・再発の危険性があるという問題点がありましたが、近年ではESDの開発、進歩によって、がんの大きさにかかわらず、一括切除可能となってきています。
放射線治療
放射線治療は、進行がんや再発したがんなどに適用します。放射線でがん細胞を直接破壊し、がんの進行を抑えることが目的です。たとえば、進行がんで手術が不可能な患者に対して、放射線治療と薬物療法を併用することでがんの縮小を図るケースがあります。放射線治療は通常、外来で通院しながら行うことが可能です。
放射線治療の副作用は治療期間中だけではなく、治療後数ヶ月以降にも現れます。治療期間中は全身の倦怠感、胃炎や腸炎、吐き気、嘔吐、軟便、下痢などです。治療後数ヶ月以降に現れる副作用としては、胃潰瘍、出血、腸閉塞、腎機能障害などですが、重篤な症状が起こるケースは稀です。
薬物療法(抗がん剤)
薬物療法には、「進行・再発胃がんに対する化学療法」と、「術後補助化学療法」があります。さらに、がんの転移状況に応じて、手術前に行う「術前補助化学療法」もあります。胃がんには、細胞障害性抗がん薬、分子標的薬を単独または組み合わせて使用します。薬の投与方法は、点滴または内服です。
細胞障害性抗がん薬は、がん細胞の増殖を抑制するために、細胞の分裂過程を妨害する薬です。進行した胃がんに対して使用されることが多く、がん細胞の増殖を止め、症状を和らげる効果があります。
分子標的薬は、がん細胞が持つ特定のタンパク質や成長因子をターゲットにして攻撃する薬です。がん細胞の増殖に関与する特定の分子を標的にするため、正常な細胞への影響を最小限に抑えつつ、がん細胞を攻撃することができます。
免疫療法
免疫療法は、患者の免疫システムを利用してがん細胞を攻撃する治療法です。2022年7月時点で、胃がんに対して有効性が証明されている免疫療法は、免疫チェックポイント阻害薬を使用する方法のみです。その他の免疫療法に関しては、胃がんに対して効果が科学的に証明されているものはありません。免疫チェックポイント阻害薬は、薬物療法(化学療法)の1つとして位置づけられています。
免疫チェックポイント阻害薬は、がん細胞が免疫システムからの攻撃を逃れるメカニズムをブロックし、免疫細胞が再びがん細胞を認識し攻撃できるようにします。ただし、免疫療法はすべての患者に適応されるわけではなく、がんの性質や患者の免疫状態に基づいて適応が慎重に検討されます。
自分や家族が胃がんになった時に知っておきたいこと

自分や家族が胃がんと診断された時は、病気の治療だけでなく、精神的なケアや経済的なサポートを受けることも重要です。次のように対応しましょう。
正確な情報の収集
インターネットには多くの情報があふれていますが、信頼性の低い情報も存在します。たとえば、民間療法や根拠のないサプリメントなどが広まっていることがあります。こうした情報に惑わされることなく、国立がん研究センターや各種専門機関、がん診療連携拠点病院など、信頼できる医療機関が提供する情報を収集しましょう。
また、担当医とのコミュニケーションも重要です。たとえば、手術を検討している場合には、治療の選択肢やリスク、副作用について詳細に説明を受け、納得できるまで質問をすることが大切です。情報提供を受ける際は、メモを取ることに加え、家族と一緒に話を聞いておくと不安が軽減され、より自身に合った判断ができるようになります。
心のケア
がんと診断されると、本人だけでなく家族も大きな精神的負担を抱える場合があります。特に「がん=死」という恐怖や、治療過程での身体的な負担を考えると、精神的なサポートは不可欠です。
たとえば、診断後のショックや不安が大きい場合、精神科や心療内科の専門医に相談することが推奨されます。また、医療機関ではがん患者向けのカウンセリングや、がんサポートグループなどのコミュニティを紹介されることもあります。同じ病気と闘っている他の患者や家族と交流し、支え合うことで孤立感を軽減できるでしょう。
また、家族としては、患者への「頑張って」や「大丈夫」という言葉がプレッシャーになることもあるため、寄り添って気持ちを共有し、必要な時にだけ助けを求めるスタンスを取ることも大切です。
保険や経済的サポートを確認する
がん治療には高額な費用がかかることが多いため、経済的な準備や公的支援制度の確認が重要です。まず、高額療養費制度について確認しましょう。高額療養費制度は、月々の医療費が一定額を超えた場合、その超過分が払い戻される制度です。たとえば、治療費が50万円かかった場合でも、高額療養費制度を適用すると実質的な自己負担が10万円程度で済むケースがあります。
また、医療費控除も知っておきたい制度です。年間の医療費が一定額を超える場合に、確定申告で税金の一部を控除でき、税金負担を軽減できます。そのほか、加入している健康保険やがん保険などがある場合は、その内容を再確認し、入院費や治療費がカバーされる範囲を明確にしておくことも大切です。保険会社に直接問い合わせることで、詳細な補償内容を確認できます。
高額な治療費が必要になる場合、生命保険を売却することも一つの選択肢です。買取サービスを利用すれば、解約返戻金よりも高い金額で買い取ってもらえる可能性があります。詳しくは、「生命保険は売却できる?売る方法を解説」をご覧ください。
胃がんと診断されたら適切に対応を!
胃がんは早期発見と適切な治療で予後を大きく改善できる一方、進行すると治療が難しくなり、生存率や余命が短くなることが多い病気です。この記事では、胃がんの原因や症状、治療法、各ステージごとの生存率について解説しました。自分や家族が胃がんと診断された場合、正確な情報の収集、心のケア、経済的なサポートの確認を含めた総合的な準備が重要です。
適切に対応し、最善の治療を受けることで、より良い生活の質を維持できるよう努めていきましょう。
・甲斐沼先生より
胃がんはがんによる死因の上位を占めていますが、早期発見および早期治療につなぐことが出来れば、比較的予後が良い疾患です。
心配であれば、消化器内科など専門医療機関を受診しましょう。
「マネックスの保険買取」は、マネックスグループ株式会社(東証プライム上場)の100%子会社であるマネックスライフセトルメント株式会社が運営する、生命保険の生前買取サービスです。
ご相談・査定は無料です。無理な勧誘は一切ございません
▼この記事の監修者
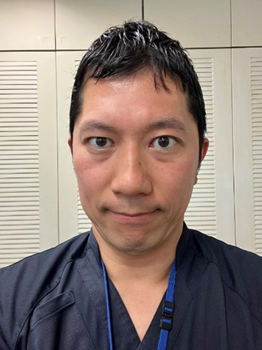 甲斐沼孟(かいぬま まさや)
甲斐沼孟(かいぬま まさや)
甲聖会紀念病院理事長 2007年
- 2007年 大阪市立大学(現:大阪公立大学)医学部医学科 卒業
- 2009年 大阪急性期総合医療センター 外科後期臨床研修医
- 2010年 大阪労災病院 心臓血管外科後期臨床研修医
- 2012年 国立病院機構大阪医療センター 心臓血管外科医員
- 2013年 大阪大学医学部附属病院 心臓血管外科非常勤医師
- 2014年 国家公務員共済組合連合会大手前病院 救急科医員
- 2021年 国家公務員共済組合連合会大手前病院 救急科医長
- 2023年 TOTO関西支社健康管理室産業医
膵臓がんの余命はどれくらい?ステージ別の生存率を解説

膵臓がんは、がんの中でも特に予後が悪いとされるがんの1つです。その理由として、早期発見が難しく、診断時にはすでに進行しているケースが多いことが挙げられます。膵臓がんと診断された際、生存率はどの程度か、どのような治療法があるのかを知っておくことは、患者や家族にとって重要です。
本記事では、膵臓がんの各ステージ別の生存率や治療法について詳しく解説します。
「マネックスの保険買取」は、マネックスグループ株式会社(東証プライム上場)の100%子会社であるマネックスライフセトルメント株式会社が運営する、生命保険の生前買取サービスです。
ご相談・査定は無料です。無理な勧誘は一切ございません
膵臓がんとは
膵臓は、胃の背後に位置する長さ約20cmの細長い臓器で、主に食物の消化を助ける膵液を分泌する外分泌機能と、血糖値を調節するインスリンなどのホルモンを分泌する内分泌機能を持ちます。膵臓がんの多くは、膵管に発生する腺がんというタイプです。膵臓がんは、がんが小さいうちは症状が現れにくく、発見が遅れがちです。
膵臓がんの特徴や症状について詳しく見ていきましょう。
膵臓がんの特徴
膵臓がんの特徴は、早期発見が非常に難しいという点です。膵臓は体の深部に位置しており、がんがある程度進行するまで症状がほとんど現れないため、発見時にはすでにステージ4になっているケースが多く見られます。また、膵臓がんは周囲の臓器やリンパ節に早く転移する傾向があり、手術で完全にがんを取り除くことが困難になることも特徴です。
・甲斐沼先生より
膵臓という臓器は腹部の背中側に位置しており、万が一膵臓がんを発症しても初期段階では自覚症状が乏しく発見されにくい疾患と言われています。
膵臓がんは早期から周囲の組織を破壊しながら進行していくため、腹部や背部の疼痛症状、食欲不振などの症状が現れて検査を受けた段階ではすでにかなりステージが進んだ状態である場合も決して少なくなく、発見された時点で手術切除が可能なケースは稀です。
膵臓がんの症状
膵臓がんの症状は、初期段階ではほとんど現れないため、がんが進行するまで自覚することは難しいとされています。膵臓がんが進行すると、次のような症状が現れます。
腹痛や背中の痛み
膵臓が体の深部に位置しているため、腫瘍が大きくなるとお腹だけではなく背中にまで痛みが現れることがあります。特に、食後や横になったときに痛みが増すことが多く、長期間続く場合は注意が必要です。
黄疸(おうだん)
膵臓がんが胆管を圧迫することで、胆汁の流れが妨げられ、皮膚や白目が黄色くなります。また、尿が茶色くなることもあります。黄疸が見られた場合は、すぐに医療機関に相談することが重要です。
体重減少や食欲不振
腫瘍が膵臓の消化機能を妨げるため、消化不良や食欲の低下が起こり、結果として体重が急激に減少します。特に、短期間での体重減少は注意が必要です。
腹部膨満感(お腹が張る感じ)
腫瘍が膵臓や周囲の臓器に影響を与えることで、食後にお腹が張ったように感じたり、満腹感が続いたりすることがあります。
糖尿病の発症や悪化
膵臓はインスリンを分泌する臓器でもあるため、がんの影響でインスリンの分泌に異常が起こり、血糖値の調整がうまくいかなくなり、糖尿病の発症や悪化が見られることがあります。
膵臓がんの余命は?ステージ別の生存率

膵臓がん全症例の10年生存率は5.8%です。純粋に「がんのみが死因となる状況」を仮定して計算した「ネット・サバイバル」における膵臓がんのステージ別の10年生存率を解説します。
出典:国立がん研究センター「院内がん登録2011年10年生存率集計 公表 小児がん、AYA世代のがんの10年生存率をがん種別に初集計」
膵臓がんステージ0(0期)
ステージ0の膵臓がんは、がんが膵管の内側の粘膜層に留まっている初期段階を指します。がんはまだ膵臓の外に広がっておらず、転移のリスクも非常に低いです。この段階で膵臓がんを発見できることはまれですが、検診や偶然の発見によって診断されることがあります。
膵臓がんステージ1(I期)
ステージ1の膵臓がんでは、がんが膵臓内に留まっており、腫瘍が多少大きくなった状態です。リンパ節や他の臓器への転移はまだ見られません。この段階で手術が行われた場合、がんを完全に切除することができる可能性が高く、術後の補助療法(化学療法)によって再発リスクを下げることも期待されます。ステージ1の膵臓がん患者の10年生存率は約31.4%です。
膵臓がんステージ2(II期)
ステージ2では、がんが膵臓の壁外へと進展しているものの、腹腔動脈や上腸間膜動脈といった太い主要動脈へは及んでいない状態です。周囲のリンパ節に転移が見られる場合もあります。しかしながら他の臓器には転移していないため、手術が可能なケースが多いでしょう。ステージ2の膵臓がんの10年生存率は約10.3%です。
膵臓がんステージ3(Ⅲ期)
ステージ3の膵臓がんは、がんが膵臓の壁外に広がり、腹腔動脈や上腸間膜動脈へ浸潤している状態です。リンパ節へ転移しており、いつ他の臓器に転移するかわかりません。手術が困難なケースも多々あります。10年生存率は3.2%です。
膵臓がんステージ4(Ⅳ期)
ステージ4は、膵臓がんが他の臓器(肝臓、肺など)に転移した状態です。手術による治療はほとんど行われず、主に化学療法や放射線療法、免疫療法を行います。10年生存率は0.6%です。
膵臓がんの治療方法
膵臓がんの治療法は、がんのステージに応じて異なります。ステージが進んでいるほど手術が難しくなり、薬物療法や放射線療法が主な治療法となることが多いです。治療法の選択は、がんの進行具合だけでなく、患者の体調や生活環境にも影響されます。膵臓がんの治療法について詳しく見ていきましょう。
手術
がんが膵臓内に限局している場合に限り、手術を行います。膵臓がんの手術には、膵頭十二指腸切除術や膵体尾部切除術、膵全摘術などがあり、がんの部位や進行度に応じて手術の種類を選択します。
膵頭十二指腸切除術は、膵頭部にがんがある場合に行う手術で、膵頭部に加えて十二指腸や胆管、胆のうを一緒に切除します。がんが胃や血管に近い場合は、それらの一部も切除されることがあります。近年では、胃を完全に残す「幽門輪温存膵頭十二指腸切除術(PPPD)」や大部分を残す「亜全胃温存膵頭十二指腸切除術(SSPPD)」が行われることが増えてきています。
術後は、膵臓を小腸に再びバイパスして膵液が流れるように再建手術を行いますが、手術後は膵液や胆汁が漏れるリスクがあり、感染症や腹膜炎が起こる可能性があるため、注意が必要です。
膵体尾部切除術は、膵臓の体部や尾部のがんを切除する手術です。通常、脾臓も一緒に摘出しますが、消化管自体は切除しないため、再建手術は不要です。しかし、手術後には膵液漏れや出血などのリスクがあり、術後の回復期間には適切なケアが求められます。
がんが膵臓全体に広がっている場合には、膵臓全体を摘出する「膵全摘術」を行います。インスリンを分泌する膵臓が完全に除去されるため、術後に糖尿病を発症することがあります。また、消化酵素が分泌されなくなるため、消化吸収に障害が出ることもあり、インスリン療法や消化酵素剤の使用が必要となります。
放射線治療
膵臓がんの放射線治療には、「化学放射線療法」と「症状緩和を目的とした放射線治療」があります。
化学放射線療法は化学療法と放射線治療を併用する治療法で、手術が難しい局所進行切除不能膵臓がんの場合に行われます。化学療法を組み合わせることで放射線治療の効果を高め、がんの進行を抑えることが期待されます。また、粒子線治療(重粒子線治療や陽子線治療)などの高度な放射線治療も行われることがありますが、実施できる施設は限られているため、治療を希望する場合は担当医に相談することが必要です。
症状緩和を目的とした放射線治療は、手術ができない膵臓がんや、遠隔転移がある場合に、痛みを和らげるために行います。
放射線治療では、副作用として皮膚の色素沈着や吐き気、食欲不振、白血球の減少などが見られることがあります。まれに胃や腸の粘膜が傷ついて出血し、黒色便が出ることもあるため、治療中や治療後は体調の変化に注意することが大切です。
薬物治療
膵臓がんの薬物治療(化学療法)では、主に細胞障害性抗がん薬を使用し、がん細胞の増殖を抑制します。治療の状況によっては、分子標的薬や免疫チェックポイント阻害薬が併用されることもあります。
分子標的薬は、がん細胞が増殖するのに必要な特定のタンパク質や分子を標的にして攻撃します。がん細胞をピンポイントで狙うため、正常な細胞への影響を最小限に抑えられるのが特徴です。
免疫チェックポイント阻害薬は、患者の免疫システムががん細胞を認識し、攻撃できるようにする薬です。膵臓がんにおいては、MSI-High(マイクロサテライト不安定性が高い)やTMB-High(腫瘍遺伝子変異量が多い)など特定の遺伝子変異がある場合に、適用します。
薬物療法は、がんの進行度や体調に応じて、さまざまな薬を組み合わせて行われます。術前補助化学療法や術後補助化学療法など、手術前後に薬物療法を行うことで再発リスクを低減させることが期待できます。また、手術が難しい場合や再発した際には、一次化学療法や二次化学療法として使われ、症状の緩和や延命を目指します。
薬物療法の副作用としては、吐き気、脱毛、しびれ、口内炎、下痢などが一般的に見られますが、これらの副作用を軽減するための薬も開発されています。担当医と十分に相談し、個々の状況に応じた最適な治療法を選択することが重要です。
免疫療法
免疫療法は、免疫システムを活性化させることで、がん細胞を攻撃して小さくする治療法です。膵臓がんにおいて、2023年3月時点で、科学的に効果が証明されている免疫療法は、免疫チェックポイント阻害薬を用いた治療法のみです。免疫チェックポイント阻害薬は、薬物療法の1つに位置づけられています。
膵臓がん患者と家族が知っておくべきこと

膵臓がんと診断された場合、患者とその家族にとって多くの不安や疑問が生まれることでしょう。以下では、膵臓がんに関する重要な情報や、知っておくべき公的サポートについて解説します。
膵臓がんに関する情報
膵臓がんの治療や予後について、信頼できる情報源から正確な情報を集めることが大切です。インターネット上にはさまざまな情報があふれかえっていますが、誤った情報や信頼性の低い内容も含まれています。
こうした情報に惑わされることなく、国立がん研究センターやがん専門の医療機関が提供する信頼性の高いデータに基づいて判断することが大切です。
また、膵臓がんには手術、放射線治療、薬物治療、免疫療法などさまざまな治療法がありますが、患者ごとに最適な治療法は異なります。したがって、担当医との十分な話し合いが重要です。
患者のケアと家族のサポート
膵臓がんは進行が早く、治療や体調の変化が急激に起こることが多いです。そのため、患者だけでなく、家族も大きなストレスを感じます。たとえば、突然の体調悪化や予期せぬ症状の出現は、患者と家族に強い不安をもたらします。精神的な負担を軽減するために、心のケアが欠かせません。必要であれば、精神科や心療内科の専門家に相談し、適切な治療を受けることも大切です。
家族としては、無理に患者を元気づけるよりも、寄り添い、気持ちを共有する姿勢が求められます。公的サポート
膵臓がんの治療には高額な医療費がかかることが多いものの、公的サポート制度を利用することで経済的な負担を軽減できます。まず、高額療養費制度を活用すれば、1か月の医療費が一定額を超えた場合、その超過分が後から返還されます。たとえば、治療費が40万円かかった場合でも、制度を適用すると自己負担額が10万円程度に抑えられることがあります。
また、医療費控除を利用すれば、年間の医療費が一定額を超えた場合、確定申告を通じて税金の一部が還付される可能性があります。
さらに、加入している医療保険やがん保険の内容を確認することも重要です。治療費や入院費がどの程度カバーされるのかを把握し、必要に応じて保険金を請求しましょう。
がんに罹患してどうしても高額な治療費が必要になった時などお金の不安がある場合は、生命保険の買取サービスの利用も選択肢の1つです。生命保険の買取金額は解約返戻金よりも高い可能性があり、まとまった現金を得ることができます。生命保険の売却方法の詳細は、「生命保険は売却できる?売る方法を解説」をご覧ください。
進行が早い膵臓がんにどう対処するか
膵臓がんは早期発見が難しく、進行が早いがんです。本記事では、膵臓がんの各ステージ別の生存率や治療法、知っておきたいことについて解説しました。
がん治療は長期に及ぶこともあるため、経済的負担を軽減するために公的制度を利用したり、保険に加入しておいたりといった対策が必要です。膵臓がんと診断された際は、今回解説した内容を参考に、適切な対応を心がけましょう。
・甲斐沼先生より
腹痛、背部痛、食思不振、嘔気、嘔吐、下痢、体重減少、黄疸など膵臓に関連する症状に該当している際には、膵臓がんなどを早期発見して速やかに治療開始することで、症状進行の抑制や合併症予防が期待できます。
腹部症状を中心として心配な症状が続いている方は、消化器内科など早急に専門医療機関を受診して相談するように心がけましょう。
「マネックスの保険買取」は、マネックスグループ株式会社(東証プライム上場)の100%子会社であるマネックスライフセトルメント株式会社が運営する、生命保険の生前買取サービスです。
ご相談・査定は無料です。無理な勧誘は一切ございません
▼この記事の監修者
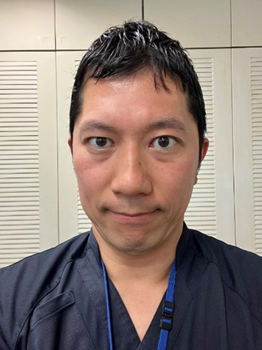 甲斐沼孟(かいぬま まさや)
甲斐沼孟(かいぬま まさや)
甲聖会紀念病院理事長
- 2007年 大阪市立大学(現:大阪公立大学)医学部医学科 卒業
- 2009年 大阪急性期総合医療センター 外科後期臨床研修医
- 2010年 大阪労災病院 心臓血管外科後期臨床研修医
- 2012年 国立病院機構大阪医療センター 心臓血管外科医員
- 2013年 大阪大学医学部附属病院 心臓血管外科非常勤医師
- 2014年 国家公務員共済組合連合会大手前病院 救急科医員
- 2021年 国家公務員共済組合連合会大手前病院 救急科医長
- 2023年 TOTO関西支社健康管理室産業医
