コラム
生命保険は売却できる?売る方法を解説

がんに罹患して、今後の治療費や生活費に不安を感じている、加入している生命保険の保険料を支払っていけるか不安という方は、生命保険買取サービスの活用を検討してみましょう。生命保険買取サービスとは、現在加入している生命保険を買い取ってもらい、買取代金が受け取れるサービスのことです。この記事では生命保険買取サービスのメリット・デメリット、生命保険を売却する流れを解説します。
「マネックスの保険買取」は、マネックスグループ株式会社(東証プライム上場)の100%子会社であるマネックスライフセトルメント株式会社が運営する、生命保険の生前買取サービスです。
ご相談・査定は無料です。無理な勧誘は一切ございません
生命保険の買取サービスとは?
生命保険の買取サービスとは、加入している生命保険を、生命保険買取サービス会社(以下、買取会社)に買い取ってもらうサービスのことです。
申込者は買取会社から、保険の買取代金を受け取ります。買い取られた後の保険料の負担は買取会社が行い、保険が継続します。また保険を買い取った後に、被保険者に万が一のことがあった場合、保険金を買取会社が受け取る仕組みです。
一旦、買取会社から受け取った買取金額は、いかなる理由があっても返済義務はありません。ただし事前に申告した内容に虚偽があるなど、買取契約に定められた事項に違反する場合には、買取金額の返還を求められる場合があります。
買取会社に保険を買い取ってもらうことで、解約返戻金よりも高く買い取ってもらえる可能性があります。解約返戻金とは、保険を解約したときに戻ってくるお金のことです。
また保険契約の買取全体を通じて、利用者が負担するのは、医療機関から診断書を取得する費用などの事務的な経費程度になります。
どういった人が生命保険買取サービスを使うの?
生命保険の買取サービスは、もともとAIDS患者の生活費や医療費の不足の悩みを解消するために、1980年代にアメリカで生まれたサービスです。
その後アメリカでは、高齢者が老後生活を補うための財産処分方法としてや、事業売却や役員の退任で死亡保障が不要になった経営者保険など、買取範囲が広がっています。
一方、日本の生命保険買取サービスは、主に以下のようなケースでまとまったお金を受け取りたいときに活用できます。ただし買取会社によっては、対応していないケースもあります。
- 保険料負担が重く、保険をこれ以上継続することが困難
- 家族に資産を遺す必要がなく、残りの人生を充実させたい
- 介護資金・介護施設入居資金が必要になった
- 高度な治療を受けるために、高額な治療費が必要になった
- まとまった資金が必要になった
- 法人で、役員保険が不要になった、または保険料の支払いを停止したい
アメリカの保険買取の市場規模
生命保険買取が誕生したアメリカにおける市場規模は1,000億円前後で、買取金額ベースでは概ね拡大傾向です。
アメリカのライフセトルメント業界団体であるLISA(ライフ・インシュアランス・セトルメント協会)は、2023年の市場データ収集調査で、アメリカのシニアが生命保険を売却することにより、解約返戻金(CSV)の6倍となる総額8億4200万ドル(約1250億円)を得たと発表しました。生命保険を売却する「ライフセトルメント」の取引件数は前年よりわずかに増加しており、この売却方法がシニア層に大きな経済的利益をもたらしていることが明らかになりました。
アメリカでは生命保険の買い取りを公的に推奨していることもありますが、世界第三位の保険大国である日本においても、数百億円規模の市場が期待できます。
生命保険を売却するメリット・デメリット

生命保険買取サービスを利用すると、解約返戻金以上の現金が受け取れる可能性がある、保険料の支払いが不要になるなどのメリットがあります。しかし受け取れる保険金額が減ってしまう、家族への保障がなくなってしまう、健康な方にとって不利になるといったデメリットもあります。
以下、生命保険買取サービスのメリット・デメリットについて詳しく紹介します。
メリット1:現金を得られる
生命保険を買い取ってもらうことで、まとまった現金を得られます。
例えばがんの治療費が必要なうえ、治療で仕事ができず収入が減ってしまうと、加入している生命保険の保険料の支払いが難しくなります。この場合の対策として、保険の解約が挙げられますが、解約しても戻ってくるお金が少ないケースもあるでしょう。
もう1つの対策として、解約返戻金の一定範囲内まで借り入れができる契約者貸付がありますが、利息がかかるうえ、保険料の支払いは続きます。返済ができず元利(元本+利息)が解約返戻金を超えると、契約が失効または解除されてしまいます。
・金子先生より
契約者貸付で借りられる金額の上限は、どの保険会社も解約返戻金のおおよそ7~9割以内です。また契約者貸付を利用すると、保険会社が定めた利息と併せて返済しなければなりません。残債が残った状態で万が一のことがあると、保険金額から差し引かれてしまうため注意が必要です。
しかし生命保険の売却によりまとまった現金が得られれば、がんの治療費や当面の生活費に充てることができるでしょう。
しかし生命保険の売却によりまとまった現金が得られれば、がんの治療費や当面の生活費に充てることができるでしょう。
メリット2:解約返戻金よりも高い金額を受け取ることが可能
生命保険買取サービスを利用すれば、解約返戻金よりも高い金額を受け取れる場合があります。
加入している生命保険を解約しても、戻ってくるお金が少ない、あるいは定期保険のように解約返戻金がない商品に加入しているケースもあるでしょう。
また解約返戻金の金額は健康な方を前提に定められており、重病にかかったからといって金額が増えるわけではありません。
生命保険買取サービスを利用して、解約返戻金よりも高い金額で生命保険を買い取ってもらえれば、一時的に家計が厳しい時期の負担を軽減できる可能性があります。
メリット3:保険料を支払う必要がなくなる
買取会社が買取金額を支払った後は、保険会社への保険料支払いを買取会社が引き継ぎます。
そのため保険買取の手続き完了後は、申込者が保険料を支払う必要がありません。
保険買取サービスは、保険料の支払いが負担に感じている方や、病気で働けず治療費や生活費を支払っていくことが難しいケースなどに役立ちます。まとまった買取金額を受け取った後は、保険料の負担や引き落とし日を心配せず、治療に専念できる点もメリットと言えるでしょう。
デメリット1:受け取れる金額は保険金額より低い
生命保険の買取金額は、解約返戻金を上回る可能性がありますが、死亡保険金額より少なくなります。
買取の一例を紹介すると、死亡保険金額2,100万円、解約返戻金250万円の生命保険の買取額は840万円です。この場合、解約返戻金より590万円多く受け取れますが、死亡保険金に対しては1,260万円不足しています。
また保険を解約せず、最後まで保険を継続したほうが金銭的に有利なケースが多いため、本当に保険を売却するメリットがあるか十分検討が必要です。
リビングニーズ特約や、重度がん保険金前払い特約により保険金が受け取れる可能性がないかどうかも確認しましょう。
リビングニーズ特約とは、被保険者が医師に余命6ヵ月以内と告げられたら、主契約の死亡保険金の全部、あるいは一部が請求できる特約です。重度がん保険金前払い特約とは、所定のがんと診断確定され、標準的な治療では効果がないと判断されたときに、死亡保険金の全部または一部が請求できる特約です。
デメリット2:家族にお金を残せない
生命保険を売却すると、死亡保険金を買取会社が受け取ることになります。
本来、死亡保険金は、被保険者に万が一のことが起きたときに、遺された家族の生活費を保障する目的で加入します。しかし保険を売却してしまうと、万が一のことが起きても死亡保険金は家族に支払われず、死亡保険に加入した当初の目的が果たせなくなるため、注意が必要です。
なお一定の要件を満たし、買取会社が同意した場合は、その時点での解約返戻金額で保険契約を買い戻すことができます。
・金子先生より
国民年金や厚生年金に加入していた方が亡くなった場合、「遺族年金」という年金が遺族に支払われる場合があります。受け取れる遺族年金の金額は、働き方や子どもの数などによって異なります。生命保険の買取サービスを利用するときは、遺族年金の金額も踏まえて検討すると良いでしょう。
デメリット3:健康状態が良い場合には不利
生命保険買取サービスは、被保険者の健康状態が良いほど、買取金額が安くなる傾向があります。つまり健康状態が良い方は、同サービスを利用する場合、不利になるということです。
同サービスは申込者から保険を買い取った後、買取会社が保険料を負担し、被保険者が死亡すると死亡保険金を受け取る仕組みです。そのため健康状態が良い人は、保険金を受け取るまでに買取会社が多くの保険料を負担する可能性が高いため、買取金額が低く査定されます。
生命保険を売却する方法を解説

生命保険の買取は、どのような流れで進められるのでしょうか?マネックスの保険買取サービスを例に手続きの流れを5つのステップに分けて解説します。
①問い合わせ・相談から初期診断
まずは自身が加入している生命保険が買取可能か、買取会社に相談をしましょう。Webや電話から、簡単に相談と簡易査定の問い合わせが可能です。
また以下の必要な手続きと情報がそろっていれば1営業日以内で買取可能かどうかの初期検討が完了します。
必要な手続き
要配慮個人情報提供の同意
必要な情報
- 年齢
- 性別
- がんの種類
- がんのステージ(進行度)
- がんの種類・ステージが診断された(おおよその)年月
- 保険金額
- 保険料の額(保険料免除の対象である場合はその旨)
②診断書の提出
買取会社で保険契約を買い取れる可能性があると判断した場合、申込者はかかりつけ医の診断書を取り付けて、買取会社に提出する必要があります。
病院によって異なりますが、診断書を取り付ける際は5,000~10,000円程度の自己負担が必要です。また診断書の取得は数日から、長いときは1週間以上かかることがあります。
③買取の可否・金額の結果を待つ
診断書の内容や提出された書類の内容をもとに、買取会社が保険契約の買い取りの可否、および買取金額を判断します。
通常、1週間以内に回答がありますが、医師の確認などがあると、さらに時間がかかる場合があります。なお、仮に保険契約の買い取りができなくなった場合でも、診断書作成費用を買取会社に負担してもらうことはできません。
④買取内容の合意
買取会社で保険契約の買い取りが可能となった場合でも、すぐに買い取ってくれるわけではありません。買取会社は、必要であれば面談を行い、家族や保険金受取人といった関係者の合意を取り付けます。関係者の合意を得た後、契約締結や重要事項説明等必要な手続きを行います。
通常であれば手続きは1週間程度で完了しますが、対面で実施する場合は、もう少し時間がかかる可能性があります。
⑤買取代金の振込
保険買取の契約締結を行った後、保険会社に保険金受取人変更の通知を行います。契約締結から買取代金の振り込みまで、概ね1週間かかります。
保険買取の契約が成立し、買取代金が振り込まれた後も、定期的に被保険者の状況について買取会社への連絡が必要です。またその他の所得金額にもよりますが、買取金額によっては一時所得として課税され、確定申告が必要になる場合があります。
実際に買取額はどれくらいになるの?
自身が加入している生命保険は、どれくらいで買い取ってもらえるのでしょうか?ここではマネックスの保険買取サービスの例を紹介します。
マネックスの生命保険買取の目安
マネックスの生命保険買取は、がん患者のみの保険買取を行っています。そのため買取額は、がんの種類や現在のステージ、年齢や性別、保険金や保険料などによって異なります。
参考までに60歳男性(乳がんは女性)、がん診断日に試算、保険金額1,000万円、保険料0円(保険料免除特約※あり)で、それぞれのがんのステージ4と診断されたときの買取額の目安を紹介します。
※特定の病気で保険会社所定の状態になった場合保険料が免除される特約のこと
| がんの種類 | 買取金額の目安 |
|---|---|
| 肺がん | 850万円 |
| 胃がん | 800万円 |
| 大腸がん | 600万円 |
| 肝がん | 800万円 |
| 膵臓がん | 900万円 |
| 乳がん | 400万円 |
なお、ここで紹介した買取額はあくまでも目安のため、ステージごとの試算や詳細の試算を知りたい方は、「保険買取のお問い合わせ」ボタンより所定のフォームに移動し、必要事項を入力のうえお問い合わせください。
また契約日から2年以上経過していない契約や、関係者から同意が得られないときは、買い取りができません。
生命保険の売却に興味があればまず気軽にお問い合せを!
加入している生命保険を買い取ってもらうことで、解約返戻金以上の金額を受け取れる場合があります。万が一の保障はなくなってしまいますが、受け取ったお金を返済する必要はありません。がんに罹患して、お金の不安があるときは、マネックスの生命保険買取サービスまで気軽にお問い合わせください。
「マネックスの保険買取」は、マネックスグループ株式会社(東証プライム上場)の100%子会社であるマネックスライフセトルメント株式会社が運営する、生命保険の生前買取サービスです。
ご相談・査定は無料です。無理な勧誘は一切ございません
▼この記事の監修者
 金子賢司(かねこ けんじ)
金子賢司(かねこ けんじ)
東証一部上場企業勤務、ファイナンシャルプランナー金融に興味を持ち、資産運用やローンなどの勉強を始める。以降ファイナンシャルプランナーとして活動し、個人・法人のお金に関する相談、北海道のテレビ番組のコメンテーター、年間毎年約100件のセミナー講師を務める。趣味はフィットネス。健康とお金、豊かなライフスタイルを実践・発信しています。
<保有資格>CFP、損保プランナー、生命保険協会認定FP
【がんサバイバー体験記:後編】治療後の第二の人生は後遺症と共に。けれどいつだって解決策は自分で切り拓く 伊勢 智一さんの場合
海外赴任中に体調を崩し、がんの治療のため日本に帰国した伊勢 智一さん。家族のために強い気持ちを失わず治療に向かった伊勢さんですが、放射線治療と抗がん剤治療によって体は深刻なダメージを受けました。治療終了から13年が経つ現在、伊勢さんはどのような生活を過ごしているのでしょうか。前編はこちらから
再発はない。けれど治療後の生活は、後遺症のある体で生きていく日々。かつて当たり前だったことに困難を感じながら、自分で解決策を見出していく
「入院期間が100日を超え、その後は自宅で体力回復のための療養生活に。激減してしまった体重は少しずつ戻りつつも、歩いていても高齢者に追い抜かれるほど力を無くしてしまいました。翌年から仕事復帰をしましたが当初はリハビリ出勤のようなものでしたね。今では出張も趣味のゴルフも楽しめるようになりました。平日は朝6時半に起床、9時には出社。おおむね19時半ごろ帰宅をして寝るのは1時過ぎといったサイクルです」。
少しずつ体力を回復していきながら、現在の生活リズムとなっている伊勢さんですが、治療前と後とで体に変化がありました。
「リンパ転移対策で喉に放射線を当てたことで、唾液腺が機能しなくなり唾液が出なくなってしまったのです。それに喉もせまくなり、食事を摂ることが困難でそれは今も続いています。普通の人の半分の量を倍以上の時間をかけて食べるのですが、それでも追い付かず、自宅では夕食の完食に1時間もかかっています。
常に喉が渇くのでどうしたものかと試行錯誤しまして、結果カフェオレという解決策を発見しました。水やお茶は飲んでもすぐに胃に落ちてしまい喉が潤わないのですが、糖分と乳成分があるカフェオレはベスト。某メーカーのカフェオレ500mlを箱買いして毎日1本飲み、これまでに3000本以上消費しています。けれどそのせいで虫歯が進行してしまいました」。放射線治療の後遺症は、照射部位は違えどもおおむね伊勢さんのようにもともとの機能が失われてしまうことが多いのですが、「カフェオレ」という解決策は経験者ならではのお話です。

「それでも幸い味覚は失わなかったのですが、舌が過敏になったことで刺激物が食べられなくなりました。酸っぱいものや辛いものがダメ。水分の少ないもの、固いもの、粉状で喉に張り付くものは食べられません。いつも大量の水分で流し込むのですが、おかげで少量の食事でもお腹が張ってパンパンになるという弊害が…。そういったさまざまのことで食事が苦手になってしまいました。自分はそれでもいいのですが、食べにくそうにしている私を見ている妻に申し訳なくて。妻は食事をいろいろ工夫してくれるのですが、どうしてもスムーズに食べられないことがあります。食事の後はすべての歯の間に食べ物が詰まるので、歯磨き・うがいをしないと気持ち悪い。食後すぐに歯磨きに走るのは妻に申し訳ないなと感じつつも、どうしようもないのですよね」とのこと。味覚は残っても食べることが困難になる…。こうしたことも、経験者でないとわからず、職場や会食の機会などはつらい思いをなさってきたことと推察できます。
がんになったときも「がんが生活のすべて」にはならなかった。治療生活を支えたのは「家族を残して死ねない」という強い思い
13年の間、幸いなことに再発もなく過ごしていらっしゃいますが、がんを経験して改めて気をつけるようになったことについては、「健康第一を心がけていますが、もとより1型糖尿病で毎日血糖値を測りながらインスリンを注射し、診察も毎月受けているので、自然に健康管理はできています。長いこと生活自体がそのようになっていますね」と語ってくださいました。
伊勢さんはがんサバイバーですが、普段それを特別に意識することはありません。
「あまり意識していませんがあえて言うなら、がん対策は第一優先ではありませんでした。がんにかかった時も、5年生存率が当時50%となっていましたがまったく死ぬ気はなかったですし。それより家族を残して死ねない、無事に帰国後の家族の生活を構築しなければいけない、という思いだけで乗り切りました。当時、アメリカと日本を短期間で二往復しましたが、まったく時差ボケを感じなかったほど」。
どんな病気やその治療にも共通することかもしれませんが、がん治療は個人の状況によってさまざまです。どれくらいの期間になるのか、体調はどんなふうに変化するのか。先の読めない生活を乗り切るうえで欠かせないのは、自分の人生観を見つめなおし、それを支える大切なものや譲れないもの、あるいはこれはあきらめても仕方がないかもしれない、などといった自分なりの処方箋というべき「納得点」を見出すことなのかもしれません。
【がんサバイバー体験記:前編】上咽頭がんステージ3、仕事の夢を叶えた矢先の宣告。治療終了から13年が経過。伊勢 智一さんの場合
「がん」という病気について語るとき、「2人に1人がかかる病気です」という言われ方をします。珍しくないよ、誰でも罹患する可能性が高い病気だよ、とセットで語ることで、過度に恐れず正しい情報をもとに適切な治療をしよう、というプラスのメッセージを想起します。一方で、アメリカと比較すると日本はがんにかかる人数が増えており、乳がんで見ると日本は死亡率が上昇しています。これは先進国でも珍しい現象だそうです。
いずれにしろ、いくら治療が進化し治癒する確率が上がったとは言え、命を落とす原因のトップはいまだがんなのです。(※)全年齢の死亡原因総数。出典:厚生労働省「死亡順位」
実は身近にいらっしゃる「がんサバイバー」の方々。念願の海外赴任を叶え充実した日々でがんが発覚した伊勢 智一さんの場合
「2人に1人がかかるがん」は、それでもやはり充分な警戒が必要であること、そして、そうした性質を伴う病気だからこそ、個人それぞれの生き方や死生観、そうしたものが影響するために治療生活は千差万別となるのです。今回インタビューにご協力くださったのは、伊勢
智一さん。2009年8月に上咽頭がんのステージ3と宣告され、過酷な治療を終えたあと現在に至るまで再発もなくエネルギッシュに生活を送っています。とはいえ、治療によって後遺症が生じ、それまで気にする必要のなかった体の変化と共に生きていくことは困難や苦労、そして新たな発見もある、いわば第二の人生ともいえるのかもしれません。
伊勢さんのように、特にご自分からがん体験を積極的にお話こそしていないけれど体験者である「がんサバイバー」は、社会にたくさんいらっしゃいます。私たちはそうした1人のがん体験を知ることで、自分に、そして社会にどう活かしていくことができるのでしょうか。
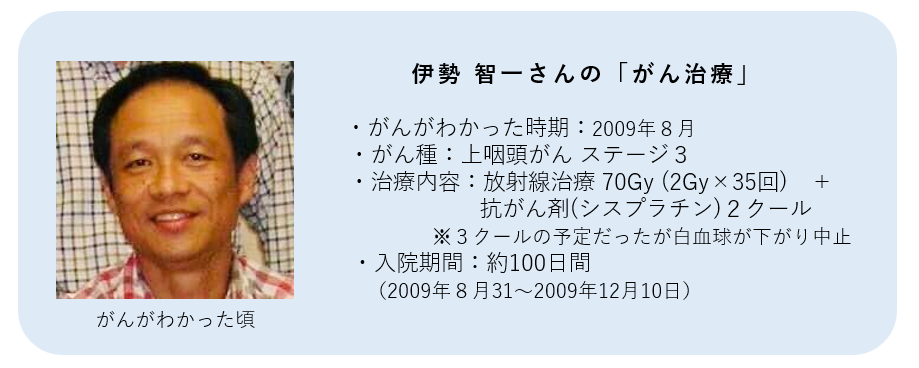
現在も上場企業で勤務中の伊勢 智一さんは1960 年生まれ、大学院を卒業後、 24 歳から一部上場企業に勤務され、第一線で活躍されているビジネスパーソンです。 24 歳での就職以来、岡山、大阪、東京、倉敷、アメリカ、兵庫と、海外赴任も含め、各地で勤務をしてきました。社会に出たころから海外で活躍することを夢に、仕事のかたわら独学で英会話の勉強を続けてきた努力家。また、30歳で糖尿病を発症し34歳で1型糖尿病と診断され、インスリン治療を行なってきたことから、一般の健康な社会人よりはご自分の体調管理や健康管理に気をつけてこられたと想像できます。
念願かなってアメリカのヒューストンで勤務をしていた2009年。当時高校生、中学生だった二人の息子さんの生活をなんとか安定して前進させることに奔走しつつ、もともと日頃から海外出張は頻繁にあり、学会で英語でプレゼンテーションすることにも慣れていた伊勢さんにとって、夢を叶えた仕事環境は刺激的で充実したものだったようです。
耳に感じた違和感が前兆。特に支障がなかったことで楽観していたものの、大学病院の診断で上咽頭がんの診断がおりる
「本場のハロウィーンやクリスマスなどを楽しみ、家族も新しい環境に慣れていったころです。ある日、左耳に違和感があることに気がつきました。飛行機を降りた時に、上空と地上の気圧差で耳がツーンとなることが誰にもあると思いますが、やがて消えるものです。ところが私の左耳は詰まった感じがいつまでも取れないのです。鼻をつまんで口も閉じて息を吹くと、右耳は息が抜けましたが左は抜けません。またそれ以降、ときどき出る痰に血が混じっていることがありました」。ヒューストン滞在1年、これが最初のサインと今にしてみれば思えるところですが、当時はそれ以外になんら支障もなく、現地の耳鼻科では炎症との診断で抗生剤を処方されただけだったため、本格的な診断は日本に一時帰国したときにでもすればいいだろう、と考えたと言います。
そして、「赴任一年で一時帰国した際に近所の耳鼻科で診てもらうと大学病院へ行くようにと紹介状を渡され、その後大学病院に行き詳しく調べたところ、上咽頭がんと診断されました。喉と耳の穴が合流するあたりに腫瘍ができてそれが左側にあったため、左耳が詰まる症状になっていたのです。この場所は手術で腫瘍を取ることができないため、放射線治療と化学治療(抗がん剤)の併用になると言われました。少なくとも2ケ月の入院が必要との診断で、すぐに上司に報告したのです。私としては念願叶って赴任した米国駐在をたった1年で終えることは避けたかったですし、赴任地のテキサス州ヒューストンは世界的にも医療先進地域であったため、現地での治療を希望しますと上司に伝えました。しかしその後、海外生活の長いその上司から、ヒューストンで治療生活を送ると家族の負担がより一層大きくなる、と告げられたことから現地での治療を断念し帰国して日本で治療することにしました。
これに伴い私の米国駐在の任は解かれ、日本へ帰任となってしまいました。あれほど思い焦がれた海外勤務があっけなく終わってしまい、病気になったことより海外勤務が終わったことの方が、私には大きなショックでした」。でも結果的にはこれは賢明な判断だったと今となっては思います。後述のとおり日本では100日間の入院となりましたが、アメリカでは長期入院は難しく短期間で退院させられるようですので、そうなったら家族の生活は成り立たなかったことでしょう。
伊勢さんの病状は上咽頭がん、ステージ3。2023年現在でこの状態の5年生存率は2~3期で60~80%となっていますが、伊勢さんが罹患した2009年当時、上咽頭がんのステージ3では5年生存率は今よりも低い状態でした。それくらい、がんの治療の進歩は非常なスピードで進化していいます。ご自分で当時、病気についてどのくらいの情報を得ていたのでしょうか?
66kgの体重が49kgにまで減少。放射線と抗がん剤の過酷な副作用に苦しんだ過去。それでも「もっともつらかったのは家族のケアをできなかったこと」
「ネット検索のみでしたが、そのとき必要な情報は充分得られたと思っています。というか、実際にはネット検索をするしか時間がなかった、というのもありました。あとは治療を受けることになる大学病院の診断時の話など、セカンドオピニオンは受けませんでした。治療内容は放射線治療 70Gy
(2Gy×35回)、抗がん剤のシスプラチン投与を3クール行うというものでした。当時、病気や治療に関して不安はあったものの疑問を抱く余地はなく、とにかく一刻も早く病気を治して仕事復帰すること、そして家族の生活を立て直すこと、これしか念頭にありませんでした。お金の面もがん保険に入っていましたがから個室で入院もできましたし、懸念はありませんでした。
始まった放射線治療は痛くもかゆくもありませんでしたが、回数を重ねるにつれ喉全体が口内炎となり、ひどい痛みで水も飲めなくなってしまいました。そのうえ、抗がん剤の副作用で何かひと口食べても吐き気に襲われ、まったく口から栄養を摂れなくなってしまい、抗がん剤治療も本来3クール予定だったのですが、抗がん剤の作用で下がった白血球数がなかなか戻らなかったため、2クールで中止になったのです」。
このとき、入院前に66 kg あった伊勢さんの体重は49kg まで減ってしまい、白血球数も大幅に減少していたことから体力を回復させるまで入院が必要となり、入院生活は3ヶ月を超えたのでした。屈強な働き盛りの男性の体重が49kgにまで落ちるほどダメージを得た治療は、想像に余りある過酷さです。やはり体調が一番つらかったことになるのでしょうか。
「いえ、もちろん治療は本当につらかったのですがそれ以上に、海外赴任から即入院となってしまったことで家族のケアがまったくできなかったことがしんどかったです。とくに長男の高校編入がなかなか決まらなかったことが心配でたまりませんでしたねぇ」。今では二人の息子さんも社会人になり、確実に歳月は過ぎていきます。
治療を終え今年で13年、次回は治療以降の伊勢さんの生活についてお話をお聞きします。
東京都:「お金」を学ぼう!アンバサダー就任式開催。「国際金融都市・東京、都民の金融リテラシーを高めたい」
東京都は、都民の安定的な資産形成に向けて金融リテラシーの向上を推進しています。都民がお金について考え、賢く活かす第一歩を後押しすることを目的として、新たに「『お金』を学ぼう!アンバサダー」を創設、本日8月29日(火)、都庁にて「『お金』を学ぼう!アンバサダー」の就任式が開催されました。
無関心層や特に若者に向けて働きかけていくことを目的とし、アンバサダーに選ばれたのはタレントの山之内 すずさんとフリーアナウンサーの青木 源太さんです。

小池 百合子都知事より、アンバサダーお二人に任命証が交付されました。



山之内さんはSNSの総フォロワー数が110万人とのことで、若い世代への情報発信力が期待されています。対する青木アナウンサーは、投資歴15年とのことで山之内さんいわく「投資についてわからないことは全部青木さんに聞くと教えてくれる!」とのことでした。
任命証を受け、「2人でこれから力を合わせて若い方を中心に、お金について学ぶ情報発信をしていく」と笑顔で宣言していました。
山之内さんは「私はこれから資産運用をしようとしている。芸能界に入って5年目、貯金はできるが資産運用はやってみたいけれど、正しい情報を選択して何から始めたらいいのか、と思っていた。今回、アンバサダーとして私自身も勉強していきたい。また、投資の大先輩である青木さんからも学びながら発信していこうと思う」と、意気込みを語りました。


自動車販売店に保険代理店業務を禁止してはいけない理由
ビッグモーター関連の報道が止まりません。
次から次へと信じられないような報道がなされており、事実であったとすれば厳しく責任を問われることは間違いないでしょう。また、単なる個社の問題のみならず、構造的な問題についての意見も増えてきています。そのなかで、多少気になる意見があったので解説しておきたいと思います。
それは、「自動車販売店に保険代理店をさせてはいけない」という意見です。たとえば、弁護士で元大阪府知事の橋下徹氏は「大きな車の販売会社はもう保険代理店としては認めないという法律を作るしかない。」と発言されています。(出典:https://toyokeizai.net/articles/-/691136?page=3)
これは利益相反(本来契約者の利益のために働くべき保険代理店が、自身の利益のために逆に契約者に損害を与えてしまうこと)を防ぐ観点からは一理あるのですが、実際にこのような法規制をしてしまえば、さらに大きな弊害が生じると思われます。
自動車販売店が保険代理店をできなくなったとき、何が問題となるのか
それは、自動車販売店が自動車保険を売れなくなれば、無保険の自動車が公道に出てしまう可能性が高くなるのではないかということです。通常、自動車を購入する場合、その購入店で自動車賠償責任保険(強制保険)に加入するとともに、任意の自動車保険への加入を勧められることになります。もし自動車販売店が保険を販売できなくなれば、他の代理店で加入しなければならないことになります。
自賠責は法令で加入が義務付けられていますので、常識的な自動車販売店であれば、自賠責への加入が確認されない限り納車しないというオペレーションになると思いますので、さすがに自賠責に加入していない自動車が公道に溢れることはないとは思いますが、問題は任意保険です。
自動車を購入しようと思ったことがある方は、任意保険の重要性を繰り返し聞いているはずです。自賠責では仮に他者に損害を与えた場合に損害の全額を補償することは難しく、損害の程度によっては被害者が泣き寝入りをしなければならないことは十分考えられます。そのため、任意保険に対人・対物無制限で加入することにより被害者に十分な補償ができるようにしておくことは、ドライバー個人を守るためではなく、被害者を守るための社会的な責任であるといえます。
自動車販売店が保険代理店をできなくなれば、ほぼ確実に任意保険に加入していない自動車が増えることになるでしょう。また、それこそビッグモーター社のように倫理感に欠ける自動車販売店であれば、自賠責すら加入していない自動車を納車してしまうかもしれません。
現在の任意保険の加入率は88%程度ですが、これをさらに引き上げることは引き続き重要な社会課題であり、下げることはあってはなりません。大手自動車販売会社が保険販売ができなくなれば、任意保険加入率が大きく下がってしまうことも十分に考えられます。
逆に考えれば、ビッグモーター社は損保ジャパン社と東京海上日動社が代理店委託を解消するとの報道が出ており、仮に残りの5社もこの動きに追随するとなれば、ビッグモーター社は保険の売れない中古車販売業者ということになります。ビッグモーター社は今のところ中古車販売業そのものは継続していますが、同社から任意保険未加入の自動車が大量供給されることのないように、なんらかの手立てを打つ必要があるでしょう。
今後一層バランスの取れた議論が望まれる
このように、保険商品のうちの一部には普及率を上げることに社会的なメリットがあります。
たとえば、現在日本に子育て世帯は約1,000万世帯ありますが、子育て中の親世代の毎年の死亡率がおおむね1,000分の1程度なので、大雑把に計算して毎年500世帯に1世帯は両親のどちらかが亡くなることになります。もし仮に生命保険がなければ、毎年数万人の子供が生活費を稼がなければならなくなり、本当にやりたかったことを諦めたり、チャレンジを断念したりしなければならなくなるでしょう。それは大きな社会的損失であり、生命保険を普及させることのメリットはそこにあります。
生命保険でも損害保険でも保険の募集に関しては何十年にもわたってトラブルを起こしてきているわけで、トラブルを無くすだけなら単に規制を厳しくすればいいのですが、普及させることも社会的な重要性があるのでそのバランスを取ることが難しいのです。
ビッグモーター社や代理店を委託していた損害保険会社の問題に絡んでこれからもさまざまな意見が出され、具体的な制度改正にもつながっていくかもしれませんが、こうした保険の社会的な効用にも目を配ったバランスの取れた議論が望まれるところです。
