コラム
胃がんのステージ別の余命・生存率とは?胃がんの原因や症状も解説

胃がんは、早期発見・早期治療により、余命・生存率の向上が期待できます。しかし、進行するほど治療が難しくなり、余命も短くなる傾向があります。本記事では、胃がんの原因や症状、各ステージの状態と生存率について詳しく解説します。
「マネックスの保険買取」は、マネックスグループ株式会社(東証プライム上場)の100%子会社であるマネックスライフセトルメント株式会社が運営する、生命保険の生前買取サービスです。
ご相談・査定は無料です。無理な勧誘は一切ございません
胃がんとは?原因と症状を解説
胃がんは、胃の内壁を覆う粘膜にできるがんです。進行するにつれて、粘膜から粘膜下層、固有筋層、漿膜(しょうまく)と外側へ広がっていき、最終的には周囲の臓器やリンパ節に転移します。
胃がんの原因と症状について詳しく見ていきましょう。
胃がんの原因
胃がんの原因として、さまざまな要因が考えられています。その中でも特に重要とされるのが、ヘリコバクター・ピロリ菌感染、食生活、生活習慣です。長期にわたって胃の健康に影響を与え、胃がん発症のリスクを高める要因とされています。
まず、ヘリコバクター・ピロリ菌は胃の粘膜に感染し、慢性の炎症を引き起こします。炎症が続くことで胃粘膜がダメージを受け、胃がんの発生リスクが増加します。ヘリコバクター・ピロリ菌の除菌治療によってリスクを軽減できることもあるため、検査で感染が確認された場合は医師と相談のうえ除菌治療を検討しましょう。
次に、食生活も胃がんの発症に深く関わっています。塩分の多い食品は胃の粘膜にダメージを与えるため、胃がんのリスクを高める原因となります。漬物や塩辛、味噌など塩分の高い食品は日本人が好んで食べる傾向があるため、場合によっては食生活の見直しが必要です。
また、野菜や果物の摂取が不足すると、胃粘膜が十分に保護されず、胃がんのリスクが高まります。
生活習慣については、中でも喫煙が胃がんに関わるとされています。タバコに含まれる有害物質が胃の防御機能を低下させ、胃がんのリスクを高めます。さらに、過度な飲酒も、アルコールが胃の粘膜を刺激し、炎症を引き起こすことから胃がんのリスク要因です。
胃がんの症状
胃がんは、早期段階では自覚症状がほとんどなく、症状が現れた時にはがんが進行しているケースが多いです。胃がんの症状は、胃潰瘍や胃炎など他の消化器疾患と似ているため、症状が出てもすぐに胃がんだと判断するのは難しいとされています。
胃がんで見られる主な症状について、詳しく見ていきましょう。
食欲不振
胃がんが進行すると、胃の機能が低下し、消化不良や満腹感が常にみられるようになります。その結果、食欲が減少することがあります。
胃痛や不快感
胃がんが胃の内壁から外側へ浸潤するにつれて、痛みや不快感が現れることがあります。胃潰瘍や胃炎の痛みと似ているため、診断が遅れることも少なくありません。
胃もたれ・胸やけ
胃がんにより胃の消化機能が低下すると、胃もたれや胸やけが頻繁に起こるようになります。食事をした後に、胃がすっきりせず、消化不良が続く感じや、胸の辺りが焼けるような感覚を持つことがあります。
黒色便
胃がんが進行すると、がんが胃の壁を侵食し、内部で出血が発生することがあります。胃の中で出血が起こると、血液は消化器を通過し、便が黒色(タール状)になることがあります。黒色便が見られた場合は、胃がんの進行によるものかもしれないため、すぐに医療機関で診察を受ける必要があります。
体重減少
急激な体重減少は、胃がんが進行している場合の典型的な症状です。がんが胃の消化機能に影響を与えることで、栄養の吸収が阻害され、食事の量が減るだけでなく、体内の代謝が異常を起こすことで脂肪量や筋肉量が減少するために体重が減少します。
胃がんの各ステージの状態と生存率
胃がんの進行度はステージ(病期)によって分類され、各ステージごとに生存率が異なります。全症例の10年生存率は56.8%です。
純粋に「がんのみが死因となる状況」を仮定して計算する純生存率を「Net Survival(ネット・サバイバル)」といいます。
院内がん登録2011年10年生存率の報告では、がん診療連携拠点病院などの院内がん登録データを用いて、10年生存率を算出しました。
ステージ別の基準と生存率について、詳しく見ていきましょう。
出典:国立がん研究センター「院内がん登録2011年10年生存率集計 公表 小児がん、AYA世代のがんの10年生存率をがん種別に初集計」
胃がんステージ0(0期)
ステージ0は、がんが胃の最内層である粘膜層に留まっている状態です。この段階では、内視鏡治療で完全にがんを取り除くことができ、生存率も非常に高いとされています。
胃がんステージ1(I期)
ステージ1では、がんが粘膜層か粘膜下層に留まっている状態で、リンパ節への転移はありません。10年生存率は77.6%です。
胃がんステージ2(II期)
ステージ2は、がんが固有筋層まで進行しているか、少数のリンパ節に転移が見られる状態です。この段階でも治療の成功率は比較的高く、10年生存率は48.9%です。
胃がんステージ3(Ⅲ期)
ステージ3は、がんが固有筋層を完全に越え、漿膜下層へと浸潤している状態です。リンパ節に転移が見られます。10年生存率は32.0%です。
胃がんステージ4(Ⅳ期)
ステージ4は、他の臓器にがんが転移した状態です。腹水がたまる場合、余命は短いケースが多く、治療は緩和ケアが中心となります。10年生存率は5.9%です。
がんで腹水がたまってしまった時の余命
末期がんになると、がん細胞が腹膜に広がり、腹水がたまることがあります。これは進行がんの典型的な症状で、腹水がたまると食事摂取が難しくなり、栄養状態が悪化します。腹水が見られる場合、余命は通常数ヶ月から半年程度といわれています。
ただし、腹水は余命を明確に示すものではないため、腹水がたまった時点で近いうちに亡くなると決まっているわけではありません。
胃がんの治療法
胃がんの治療法は、がんの進行度や患者の体調に応じて選択されます。胃がんの治療法について詳しく見ていきましょう。
手術治療
手術治療は、胃がんが初期段階または局所に留まっている場合に効果的な治療法です。早期の胃がんでは、内視鏡を用いてがん細胞のみを切除する「内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)」を行える場合があります。体への負担が少なく、数日で退院することが可能です。
進行した胃がんに対しては、部分的な胃切除や、がんの広がりが大きい場合には胃全摘術を行います。たとえば、胃の出口付近にがんがある場合には、幽門側胃切除術という手術で胃の下部2/3を切除し、残った胃と十二指腸、または小腸をつなげます。また、がんがリンパ節に転移している可能性がある場合には、リンパ節郭清という周囲のリンパ節も同時に取り除く手術も行います。
・甲斐沼先生より
昨今、一部の早期がんに対して、内視鏡を使ってがんを切除することが行われています。
胃がんに対する内視鏡切除術には大きく2つの方法があり、EMR(正式名称:内視鏡的粘膜切除術)とESD(正式名称:内視鏡的粘膜下層剥離術)です。
従来は、EMRにて治療が行われていましたが、大きな病変だと分割切除になり、遺残・再発の危険性があるという問題点がありましたが、近年ではESDの開発、進歩によって、がんの大きさにかかわらず、一括切除可能となってきています。
放射線治療
放射線治療は、進行がんや再発したがんなどに適用します。放射線でがん細胞を直接破壊し、がんの進行を抑えることが目的です。たとえば、進行がんで手術が不可能な患者に対して、放射線治療と薬物療法を併用することでがんの縮小を図るケースがあります。放射線治療は通常、外来で通院しながら行うことが可能です。
放射線治療の副作用は治療期間中だけではなく、治療後数ヶ月以降にも現れます。治療期間中は全身の倦怠感、胃炎や腸炎、吐き気、嘔吐、軟便、下痢などです。治療後数ヶ月以降に現れる副作用としては、胃潰瘍、出血、腸閉塞、腎機能障害などですが、重篤な症状が起こるケースは稀です。
薬物療法(抗がん剤)
薬物療法には、「進行・再発胃がんに対する化学療法」と、「術後補助化学療法」があります。さらに、がんの転移状況に応じて、手術前に行う「術前補助化学療法」もあります。胃がんには、細胞障害性抗がん薬、分子標的薬を単独または組み合わせて使用します。薬の投与方法は、点滴または内服です。
細胞障害性抗がん薬は、がん細胞の増殖を抑制するために、細胞の分裂過程を妨害する薬です。進行した胃がんに対して使用されることが多く、がん細胞の増殖を止め、症状を和らげる効果があります。
分子標的薬は、がん細胞が持つ特定のタンパク質や成長因子をターゲットにして攻撃する薬です。がん細胞の増殖に関与する特定の分子を標的にするため、正常な細胞への影響を最小限に抑えつつ、がん細胞を攻撃することができます。
免疫療法
免疫療法は、患者の免疫システムを利用してがん細胞を攻撃する治療法です。2022年7月時点で、胃がんに対して有効性が証明されている免疫療法は、免疫チェックポイント阻害薬を使用する方法のみです。その他の免疫療法に関しては、胃がんに対して効果が科学的に証明されているものはありません。免疫チェックポイント阻害薬は、薬物療法(化学療法)の1つとして位置づけられています。
免疫チェックポイント阻害薬は、がん細胞が免疫システムからの攻撃を逃れるメカニズムをブロックし、免疫細胞が再びがん細胞を認識し攻撃できるようにします。ただし、免疫療法はすべての患者に適応されるわけではなく、がんの性質や患者の免疫状態に基づいて適応が慎重に検討されます。
自分や家族が胃がんになった時に知っておきたいこと

自分や家族が胃がんと診断された時は、病気の治療だけでなく、精神的なケアや経済的なサポートを受けることも重要です。次のように対応しましょう。
正確な情報の収集
インターネットには多くの情報があふれていますが、信頼性の低い情報も存在します。たとえば、民間療法や根拠のないサプリメントなどが広まっていることがあります。こうした情報に惑わされることなく、国立がん研究センターや各種専門機関、がん診療連携拠点病院など、信頼できる医療機関が提供する情報を収集しましょう。
また、担当医とのコミュニケーションも重要です。たとえば、手術を検討している場合には、治療の選択肢やリスク、副作用について詳細に説明を受け、納得できるまで質問をすることが大切です。情報提供を受ける際は、メモを取ることに加え、家族と一緒に話を聞いておくと不安が軽減され、より自身に合った判断ができるようになります。
心のケア
がんと診断されると、本人だけでなく家族も大きな精神的負担を抱える場合があります。特に「がん=死」という恐怖や、治療過程での身体的な負担を考えると、精神的なサポートは不可欠です。
たとえば、診断後のショックや不安が大きい場合、精神科や心療内科の専門医に相談することが推奨されます。また、医療機関ではがん患者向けのカウンセリングや、がんサポートグループなどのコミュニティを紹介されることもあります。同じ病気と闘っている他の患者や家族と交流し、支え合うことで孤立感を軽減できるでしょう。
また、家族としては、患者への「頑張って」や「大丈夫」という言葉がプレッシャーになることもあるため、寄り添って気持ちを共有し、必要な時にだけ助けを求めるスタンスを取ることも大切です。
保険や経済的サポートを確認する
がん治療には高額な費用がかかることが多いため、経済的な準備や公的支援制度の確認が重要です。まず、高額療養費制度について確認しましょう。高額療養費制度は、月々の医療費が一定額を超えた場合、その超過分が払い戻される制度です。たとえば、治療費が50万円かかった場合でも、高額療養費制度を適用すると実質的な自己負担が10万円程度で済むケースがあります。
また、医療費控除も知っておきたい制度です。年間の医療費が一定額を超える場合に、確定申告で税金の一部を控除でき、税金負担を軽減できます。そのほか、加入している健康保険やがん保険などがある場合は、その内容を再確認し、入院費や治療費がカバーされる範囲を明確にしておくことも大切です。保険会社に直接問い合わせることで、詳細な補償内容を確認できます。
高額な治療費が必要になる場合、生命保険を売却することも一つの選択肢です。買取サービスを利用すれば、解約返戻金よりも高い金額で買い取ってもらえる可能性があります。詳しくは、「生命保険は売却できる?売る方法を解説」をご覧ください。
胃がんと診断されたら適切に対応を!
胃がんは早期発見と適切な治療で予後を大きく改善できる一方、進行すると治療が難しくなり、生存率や余命が短くなることが多い病気です。この記事では、胃がんの原因や症状、治療法、各ステージごとの生存率について解説しました。自分や家族が胃がんと診断された場合、正確な情報の収集、心のケア、経済的なサポートの確認を含めた総合的な準備が重要です。
適切に対応し、最善の治療を受けることで、より良い生活の質を維持できるよう努めていきましょう。
・甲斐沼先生より
胃がんはがんによる死因の上位を占めていますが、早期発見および早期治療につなぐことが出来れば、比較的予後が良い疾患です。
心配であれば、消化器内科など専門医療機関を受診しましょう。
「マネックスの保険買取」は、マネックスグループ株式会社(東証プライム上場)の100%子会社であるマネックスライフセトルメント株式会社が運営する、生命保険の生前買取サービスです。
ご相談・査定は無料です。無理な勧誘は一切ございません
▼この記事の監修者
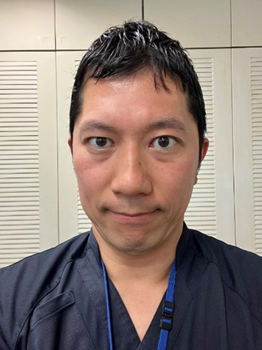 甲斐沼孟(かいぬま まさや)
甲斐沼孟(かいぬま まさや)
甲聖会紀念病院理事長 2007年
- 2007年 大阪市立大学(現:大阪公立大学)医学部医学科 卒業
- 2009年 大阪急性期総合医療センター 外科後期臨床研修医
- 2010年 大阪労災病院 心臓血管外科後期臨床研修医
- 2012年 国立病院機構大阪医療センター 心臓血管外科医員
- 2013年 大阪大学医学部附属病院 心臓血管外科非常勤医師
- 2014年 国家公務員共済組合連合会大手前病院 救急科医員
- 2021年 国家公務員共済組合連合会大手前病院 救急科医長
- 2023年 TOTO関西支社健康管理室産業医
